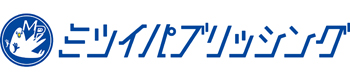- Home
- [Webマガジン]ダブリンつれづれ
- 「第24回 海のように美しい」ダブリンつれづれ / 津川エリコ
最新記事
3.142025
「第24回 海のように美しい」ダブリンつれづれ / 津川エリコ

日本へ注文した本が四十五日もかかって届いた。待っている間にアイルランドでは珍しい大雪が二度も降り、学校、会社、商店がことごとく閉鎖した。まるで国家の非常事態のようだった。大雪による輸送の停滞と混乱の中で本は紛失してしまったのではないか。一度はダブリン空港も閉鎖した。溜まった大量の郵便物が貨物船から海へ捨てられている夢を見た日、私はその同じ本をもう一度度注文した。
すると、翌日になって本が届いた。それが四十五日目だったのだ。『サン・ミケーレ物語』である。サン・ミケーレは大天使ミカエルのこと。著者はスウェーデン生まれの医者、アクセル・ムンテ。この本が最初に出版されたのは、百年近く前の一九二九年である。世界中でベストセラーになったという。日本語に翻訳されたのは六〇年代である。回想と空想が混じりあった奇妙な物語である。
十九世紀の後半にナポリでコレラが蔓延したとき、ムンテは医者として救援活動に出かけた。彼はナポリ湾に浮かぶカプリ島にある、かつてサン・ミケーレに捧げられたという中世の礼拝堂の遺跡を買い取り、そこに邸宅を建てた。
この本を読み始めた時、私は、これをできるだけゆっくり読もうと決めた。楽しみを長引かせようという算段である。ところが、ダブリンは猛烈に寒い日が続き、家の中に籠ったせいで、ゆっくり読むはずだった『サン・ミケーレ物語』はどんどん進んで行った。
そんなとき、新聞に含まれていた団体旅行のチラシに「カプリ島」とあるのが目に止まった。次の瞬間にはオンラインで衝動的に申し込み、街へ出てイタリアの地図を買った。ムンテの本を読みながらナポリやカプリ島の正確な位置を知りたいと思っていたその一方で、ダブリンの遅い春にすっかり辟易し、何処か暖かい所へ行きたいという気持ちになっていたのも確かだ。ツアーの定員は残り三人とあり、決断は〈すぐ〉でなければならなかった。その晩、家族に「このツアーに申し込みました」と宣言した。出発まで一週間。
イタリアへ出かける数日前に、友人をランチに招いていた。私は、彼女に『サン・ミケーレ物語』を「もう読んでしまったので」と差し出して勧めた。ところが彼女が帰った後で、本当に読み終わったのだろうかと気になり始めた。最後に読んだ箇所は、ムンテが出会った島の老人が死ぬところである。この老人が息を引き取る前に「海のように美しい!」と呟くのだ。それは物語の締めくくりとして、とてもふさわしいように私には思われたのだった。
海のように美しい!
アクセル・ムンテ『サン・ミケーレ物語《増補版》』久保文訳、紀伊国屋書店、1974年
この言葉をわたしは確信をもってここに書くことはできない。実に不可解な言葉だ。いったいどこからこんな言葉が出てきたのだろう。きっとまだパンの神が生きていて、森の木々が物をいい、海の水がうたい、人間がそれを聞き理解できたずっとずっと昔の忘れ去られてしまった黄金時代から木霊(こだま)のようにひびいてきた言葉なのだ。
私は本を閉じて、「海のように美しい」と呟やかないではいられなかった。
ダブリンからナポリまで三時間半。飛行時間が短いので窓側の席を取った。イタリアンアルプスと思われる雪を被った山脈の上空を飛んだ。バッグに地図が入っている。狭い座席ではそれを広げて確認することもできない。
ナポリ湾が見えた。夏目漱石がロンドンへ留学した時の、横浜からのルートを調べてみたことがある。ナポリは漱石が目にした最初のヨーロッパの都市である。彼はナポリで半日観光し、再び乗船してジェノヴァへ向かい、そこで最終的に下船しパリ行きの列車に乗りこんでいる。一九〇〇年のこと。日本からナポリへ一カ月半かかる、百年前の船旅である。
ツアーの初日、午前中はポンペイの遺跡へ。子どもの頃、火山噴火で丸ごと埋もれてしまった都市のことを最初に知った時の驚き。あれから何年経ったのか。私がもう子どもではないということにも驚かされる。こういう場所でガイドがいるのは本当に有難い。彼女に率いられて、主なところを廻る。二千年前のパン屋、浴場、食べるのにタベルナというファストフードの店の跡、野外劇場等々。赤線地帯もあり、ガイドのロベルタが二千年前の娼館のチャージはワインボトル一本くらいの値段だったという。彼女の説明はほどほどに専門的でまたユーモアもあり、英語も分かりやすい。
人と犬の石膏型が展示されている。最初にポンペイに入った発掘隊が積もった灰の中にいくつもの空洞を発見し、不思議に思ってその空洞に石膏を流しこんで型を取ってみたところ、人や犬だったということがわかったのだという。私が子どもの頃から何度か見たポンペイのうつ伏せになった人型は、実は石膏によってとられた型なのだ。ツアーは元船着き場だったところで終わった。ポンペイは港町だった。今は海が遠くに見える。火山礫と火山灰で海は三キロ向こうに遠ざかってしまったのだ。元は海だったところを出口に向かって歩いていく。
最初の自由日。一人参加のカレンと一緒にソレントへ出かけた。何も考えずに二人で素早く決めた昼食のレストランの広い中庭には、たくさんのレモンの木があった。レモンが実っているうえにレモンの花も咲いている。地中海性の気候ではそうなるのか。空はこの日、初めから青かったがここへきてレモンの木を透かして見上げると、もっと青くなったように思われた。カレンが突然叫んだ。「エリコ、貴方の後ろに豚が……」
私の後ろの木陰に豚が寝転がっていた。レストランに入って来た時、まずウサギに気付いた。それから何匹かのネコ。豚もいたのだ。「カレン、私の後ろに豚がいるなんて言ったのは私の一生であなたが初めてよ」と私は言った。白ワインを飲んで、ピザを食べた。
ツアーの四日目、ついに『サン・ミケーレ物語』の舞台となったカプリ島へ。渋滞を避けるため八時出発。ソレント港からフェリーに乗った。ドイツの作家、ジャン・パウル(Jean Paul,1763-1825)が、島の輪郭をギザのスフィンクスのようだと形容したとガイドが言った。ライオンの身体と人の頭を持った怪物は、ナポリ湾の最南端に浮かんで湾を警護しているのだろう。島に降りてミニバスに乗り換え、曲がりくねった道を上って行く。崖の斜面に沿って海へ下りて行く細く狭い石段がみえる。車のない時代のものだろう。石段の現実離れした美しさ。忘れられたように清潔だ。再びここへ来る機会があったなら、この石段を降りて行くことだろう。
『サン・ミケーレ物語』に出て来るムンテのヴィラへ辿り着く。彼は祖国、スウェ—デンへ戻る時、ヴィラをイタリア政府に寄付した。それが今、一般に公開されている。ガラス戸の書棚には、数々の言語に翻訳された『サン・ミケーレ物語』が並んでいて日本語の初版本も混じっている。彼は、裕福な患者には高い治療費を請求し、貧しい患者からはお金をとらなかったそうだ。ナポリでコレラが蔓延した時には、自分に感染するリスクを承知で救援に当たっている。奇特な人だ。
明日はダブリンに帰るという日、夕食に出て行く頃から喉が痛くなっていた。今日はワインを飲むのは止めようと決意していた。この一週間、いつも私の横に席にいたクリスがワインを注ごうとするので、喉のことを説明した。すると彼はワインのボトルのラベルを読み上げて「喉の痛みによく効く、と書いてあるよ」と言った。私は、ハンドバッグからメガネを取り出し、彼の指差した部分の小さな文字を読む振りをし「ふむふむ」と大きく頷いて、テーブルの皆を笑わせた。結局、ワインからは逃れられなかった。ツアー最後の夜である。
帰る日も暖かい。イタリアに着いてからずっと二十四度前後の日が続いてきた。毎日、青空。地中海気候というものを経験した気持ちだった。朝食の時、給仕をするホテルのウェイターやウェイトレスにさよならを言う。夕べ遅くまで働いていた人たちが、また朝七時に食堂へ出て来て働いている。ホテルで働くということは大変なことだ。
ナポリ空港、ダブリンへの出発ゲイトの小さなスクリーンに「ダブリン六℃」とある。戻って行くダブリンは冬であるらしい。到着は定刻通りだった。旅は終わった。帰宅すると二度目に注文した『サン・ミケーレ物語』が届いていた。読み終えたと思って友人に貸した後、先があったように思って気になっていた。僅かではあったがやはり先があった。その残りを読んだが、「海のように美しい」という箇所で終わっていた方がずっと良かっただろう。
津川エリコ
北海道釧路市生まれ。ダブリン在住。『雨の合間』(デザインエッグ)で第55回小熊秀雄賞受賞。小説「オニ」(『北の文学2022』所収、北海道新聞社)で北海道新聞文学賞受賞。著書に詩集『アイルランドの風の花嫁』(金星堂)、随筆集『病む木』(デザインエッグ)があるほか、詩集アンソロジー”Landing Places”, “Writing Home”, “Local Wonders”(いずれもDedalus Press)に作品所収。