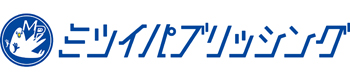- Home
- [Webマガジン]グローバルサウスの片隅で
- 「第15回 アイロン」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる
最新記事
3.212025
「第15回 アイロン」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる

家にアイロンはあるだろうか。アイロンかけは得意だろうか。毎日使っているだろうか。さすがに、家族で住んでいる方はアイロンの一台くらいお持ちではないかと思うが、今の若い方にとってこれが必須の電化用品なのかどうか、心許ない。60代半ばである私が育った家にはもちろんあったし、その後ひとりで引っ越し支度を整える時にもいつもアイロンはありはしたが、長く必須のもの、という位置にはない、まあ、あったほうがいいよな、程度の小型家電であった。
それが日々の生活に必須となり、毎日出すようになり、スチームアイロンとアイロン台は、すぐ出しやすいところに置くようになり、着ていたものを脱ぐ前にいつもスチームアイロンのスイッチをかける習慣がついたのは、40代半ば、きものを毎日着るような生活になってからだった。きものを日常着とするためには、スチームアイロンこそが必須アイテムなのである。きものや帯、帯揚げ、腰紐など、きものまわりのあれこれは、下着である裾除け(腰巻き)と肌じゅばんと足袋(それに、衿)以外は毎日洗うようなものではない。きものは季節ごとに丸洗い、何年か(10年とか)に一度洗い張りするくらいであり、毎日着たものを洗濯しないというか、できないのである。1日着ていると、しわになるし、特に夏場は汗をかくし、脱いだらこのしわをとり、汗を飛ばさなければならない。そのためにスチームアイロンを使う。
きものを脱ごうとするまえにスチームアイロンのスイッチを入れて、まだ温もりや汗の残っているままのきものにどんどんスチームアイロンをかけてしわをのばし、汗をとばして衣紋掛けにかけていく。慣れない人は、くれぐれも絹の着物に直接アイロンをかけたりしないように。当て布などをしてやっていただきたいが、きものとのつきあいが慣れてくると、だんだん感覚がわかってきて、この程度さっとかけるかんじだと、この布にもスチームアイロン、大丈夫、というのがわかってくるので、直接かけているが、これはきものをほぼ毎日着てきた私の感覚と、もしかしたらきものをいためることがあるかもしれない(アイロンでいためたことは今まで一度もないが)自己責任によってやっていることなので、誰にでもはすすめられない。ぜひ当て布を。
この脱いだ衣装にさっとスチームアイロン、というのは、きものの着方からはじまって、ほぼすべてをおしえてくれたわたしのきものメンターである日本舞踊の師範で着付けの教授である友人から、おしえてもらった。彼女からも、くれぐれも当て布をしなさいよ、と言っておしえられている。歌舞伎や日本舞踊などの舞台では、衣装はもちろんすぐに洗えるものではないから、こんなふうにして脱いだ後の衣装にスチームアイロンをかけている、というように聞いていた。2024年4月に八重山竹富島に移住し、最初の島を挙げての国の重要無形文化財である種子取祭奉納芸能で、男性の演目「太鼓」の着付けを担当した(第11回参照)。種子取祭の奉納芸能は二日間にわたって行われ、双方、午前中は「庭の芸能」と呼ばれる御嶽の前の広場で奉納される芸能、午後は、舞台芸能で、一日目は玻座間芸能保存会、二日目は仲筋芸能保存会が担当する。「太鼓」は庭の芸能の演目であり、一日目、芸能を披露した後も、御嶽への挨拶、他演目への出演もあり、半日以上衣装をつけたままですごす。二日目もまた、朝、着付けなければならないから一日目のシワはとりたいので、着付けをする公民館にスチームアイロンをもちこみ、脱いだ人のきものからどんどんアイロンをかけていた。そのほうがすっきり翌日に着られる。
ともあれ、わたしは40代半ばから着物生活に入り、スチームアイロンがどうしても日々の生活に必要になった。きものや帯にもかならずかけるが、とりわけ帯揚げ、腰紐にアイロンをかけて、まっすぐにきちっとした感じになることに喜びを感じる。旅先などで持ち合わせの下着の選択が間に合いそうにない時は、肌襦袢や裾除けにもスチームアイロンをかけて、汗を飛ばして次の日に着たこともある。ホテルに泊まると、まず、スチームアイロンとアイロン台を貸してください、とお願いする。かなり高級で上等な、自分で洗濯をすることなど絶対想定されていないようなホテルでも、アイロンは、たいてい、貸し出しアイテムにあり、たのむとすぐもってきてくれる。私はリッチモンドホテルファンで、長年通ってきた熊本や那覇の定宿は、リッチモンドホテルである。今でこそ、この手の「ちょっと設備も整って居心地の良いビジネスホテル系」のホテルはチェーン店を中心に増えてきたが、リッチモンドが登場した頃、広くて眠りやすい質の良いベッド、おざなりではない、すわりやすいチェアの完備と、仕事をして書類などを広げる余裕のある広い机、余裕のあるバスタブとトイレ、いつも少し多めに入れてくれるタオル、ドリップコーヒーがあること、など、それまでのビジネスホテルの品質と比べると実に充実していて、むしろもっと高級なホテルより仕事がしやすいので、リッチモンドがある街では、選んでリッチモンドに泊まるようになった。最近は、日本中のリッチモンドに泊まると、頼まなくても部屋にスチームアイロンを入れておいてくださるようになった。助かっています。ありがとうございます。
アイロンは、むしろ西洋社会で必須のアイテムなのかもしれない。ヨーロッパにはオーペアという若い人がイギリスなどにきて、家庭に住み込み、英語の勉強をしながら、家の手伝いをする、という制度があった。おそらく今もあるか、と思う。わたしがイギリスにいた頃だからすでに30年くらい前のことになってしまうが、その頃、イギリスにはスカンジナビア諸国や南ヨーロッパなどからオーペアの女性たちがきていた。彼女たちを雇う家は、子どものいる家が多かった。オーペアの代表的な仕事はまず、「子どもの送り迎え」や「ベビーシッター」だった。イギリスでは15歳以下の子どもは子どもだけで家にいてはいけない、ということになっている。保護者は、子どもの安全のために、15歳以下の子どもを子どもだけにしてはいけないのだ。働いている親は子どもが学校から帰ってくる時間には、まだ職場にいることが多いから、その「ベビーシッター」つまりはベビーではないけれど、子どもといっしょにいてもらうためにオーペアを雇ったりしていた。
この、15歳以下の子どもを子どもだけで家においてはいけない、という感覚は、日本に暮らしているとほんとうにわかりにくい。家は安全なところ、という発想があるから、小学校に上がるくらいの子どもになると、当然「家でお留守番」というのはできる、と親たちは思っている。昭和30年代生まれの私の世代の頃から「鍵っ子」ということばはあって、これは、学校を終えて家に帰っても家に誰もおらず、家に鍵がかかっているから、子どもは鍵を持って出かけ、鍵を開けて誰もいない家に帰る、という子どものことを指していた。「子どもが子どもだけで家にいていい。それは安全である」という前提があり、それはいわずもがなのごく普通のこと、として捉えられていたと思う。イギリスで同じことをやって、イギリス人の親に「うちの子どもが、大人のいない時間、あなたの家に遊びに行ったという。それはこの国では許されていない」と叱られた日本人の親は少なくないらしい。みんな、びっくりしていた。なぜ、だめなの?
子どもは思いもつかぬことをすることがあるから、大人の保護下にいなければならない、という感覚はいまでは共有されてきたから、小学生で家に帰っても親がいない子どもは、学童保育などに通うようになっていて、そこがまた、定員が足りないと議論されているのだから、「鍵っ子」という言葉はすでに死語になりつつある。しかしそれは、小学生のことであって、中学生になると、まあ、部活などもあるから、帰りが遅いこともあるけれど、鍵を持たせて自分だけで家にいる、ということに問題を感じる親は、まだ、いないのではあるまいか。13~15歳の子どもも、イギリスでは子どもだけにしてはいけない年齢なのであった。だから、オーペアが、必要とされていた。
子どもの送り迎えに、ベビーシッター(チャイルドシッターというべきか)、という仕事の次にオーペアに多く課されていたのが「アイロンかけ」であった。洗って乾いた服は、アイロンをかけられねばならない。ベッドリネン、テーブルリネン、タオル、なども全てアイロンをかけられることが期待されていた。大変な家事の一つなので、ここを助けてもらうことが必要、と思われていたのである。どの家にも、アイロンと、立ったままアイロンをかけることができる折りたたみ式の大きなアイロン台があった。
ラテンアメリカは現在の生活様式において、西洋社会の一部をなす地域であり、10年住んだブラジルでもアイロンは必須のものだった。ブラジルはまだ、中産階級、というか、職業人夫婦の家庭の住む家には、いわば「ワーキングエリア」というスペースがあり、お手伝いさんが住み込んだり、シャワーを浴びたりすると同時に、そこで洗濯、アイロンなどをする場所になっている。将来的にお手伝いさんがいないことが日常になっていくかも知れないが、そうなってもそういう「洗濯、アイロン」のスペースは残りそうである。そこには、しっかりしたアイロンとアイロン台がおかれ、Tシャツからタオルまでアイロンがかけられていく。父が私の住んでいたブラジルの家に半年くらいいたことがあるが、彼が一番感じ入っていたのは、Tシャツにアイロンをかけることで、おしゃれな父にはこれは真似するべきこと、とうつったようで彼は日本に帰国後もずっとTシャツにアイロンをかけていた。
Tシャツにまでアイロンをかけるのだから、いわゆるシャツにアイロンをかけるのは当然である。子どもたちの父親であるブラジル人、ウォルターは最初に出会った時から、とにかく、すごくアイロンに熱心な人だな、と思っていた。自分の着るシャツには誠に丁寧にアイロンをかけている。アイロンをかけていない服は着るべきではない、と思っている。一緒にギリシャのクレタ島に旅行した時、借りたロッジにはアイロンがなかった。彼は、台所のフライパンを熱して、フライパンの底でシャツにアイロンをかけるのであった。フライパンの底は「鉄」でできているから、文字通り「鉄=アイロン」なのである。旅行してスーツケースに入っているシャツには折り目がついているから、再度アイロンをかけて着るのである。
長男はブラジル生まれで、10歳までブラジルで育った。幼い頃から身だしなみと外見に気を使う人で、小学校4年生から日本で暮らし、おしゃれな青年に育った。父親と同じように、アイロンをせっせとかける人で、中高生の頃は、自分がアイロンをかけたいような服は母親に任せておいても、アイロンは下手だし、いつやってもらえるかわからないので、自分でやっていたのだ。父親に似ている。大学を出てビジネスマンとして仕事を始めた頃(2015年頃)はまだ、ビジネスマンはスーツを着て仕事をしていた。これがほどなく、必ずしもスーツでなくてもよい、という流れになってきて、いまではスーツを着ることがほとんどなくなったようだが、それはともかく、彼が会社員になった頃は、スーツはビジネスマンの必須アイテムであったのだ。
彼は会社の同期と二人で、会社に程近い2LDKの部屋を借りて暮らしていた。ルームメイトも結構まめな人だったようで、二人の部屋を訪ねてみると、リビングには立派なアイロンと、西洋にあるような背の高いアイロン台が設置してあった。ビジネススーツに合わせるシャツは、いまどきは形態安定のノーアイロンシャツもあるが、おしゃれなブランドシャツはノーアイロンでないことも多い。このルームメイト氏もまた、アイロンに一家言ある人で、洗濯して脱水し、干す前のシャツにアイロンをかけるようにしている。曰く、どうせ、乾かした後、しゅっしゅっと霧を吹いたり、スチームアイロンをわざわざかけたりするのなら、シャツが湿っている間にアイロンをかけた方がよい、と考えているのであった。息子も真似していた。なるほど。若い男性二人に教えられたものである。
かようにアイロンは西洋社会に必須アイテム、日本ではあまり使わなくなっている……というふうに書いているが、博物館に行ってみよ、この国でも、着物を美しく着たり仕立てたりするために、火熨斗とよばれる、炭を入れた柄杓状の物を使っていたことがわかる。宮城文の『八重山生活史』は、女性自身の視点でつぶさに生活の衣食住、女性の人生、年中行事を記録した画期的な本なのだが、そこにも、衣類の皺をとるための干し方や、寝押しをしたことなどが記載されている。寝押し、ということは、昔ながらのひだの多いスカートが制服の学校に通ったことのある女性なら、皆覚えているだろう。プリーツスカートにアイロンをかけると、てかてか光ってしまうので、寝る前にきれいにプリーツスカートを畳んで、布団の下に入れて寝押しするのである。生活がままならないような家の中学校同級生のスカートのひだは、いつもとれていたことのいたましさを、いまも忘れることができないでいる。
 三砂ちづる (みさご・ちづる)
三砂ちづる (みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮育ち。津田塾大学名誉教授、作家。京都薬科大学卒業、ロンドン大学Ph.D.(疫学)。著書に『オニババ化する女たち』『ケアリング・ストーリー』『六〇代は、きものに誘われて』『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』『少女のための性の話』『少女のための海外の話』、訳書にフレイレ『被抑圧者の教育学』、共著に『家で生まれて家で死ぬ』他多数。