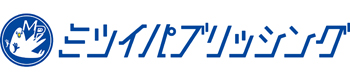- Home
- [Webマガジン]グローバルサウスの片隅で
- 「第20回 ブー(前編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる
最新記事
6.62025
「第20回 ブー(前編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる

竹富島では苧麻のことをブーと呼んでいる。苧麻はイラクサ科の多年草だそうだ。竹富では年に3回くらい採れる。もともと島で採れる衣服の繊維は、苧麻か糸芭蕉だったので、2025年現在、七十代半ば以降くらいの方は周囲に苧麻や糸芭蕉を使った衣服がたくさんあったことをまだ覚えておられる。苧麻や糸芭蕉を使った布、というのは、要するに現在で言われる上布とか芭蕉布である。苧麻を使った布で献上されるほどに質の良いものが上布と呼ばれ、織り方により中布、下布もあったという。芭蕉布とともに、人頭税時代にまさに身を削るようにして織られてきたものだ。現在ではとんでもない高級夏物着物の代表である上布や芭蕉布で、普通の方にはちょっと手のでない一桁違う値段のおきものとなるのであるが、もともとは庶民の衣服に混紡にしたりして使われていたのだ。
お話を伺った男性は、幼い頃はパンツも芭蕉布、中学校に通うときのズボンも芭蕉布でできていて、ゴワゴワしていて肌触りは悪かったが涼しかった、とおっしゃっていた。芭蕉布のパンツにズボン、なんて、なんと贅沢な、と今の感覚では思ってしまうが、日常的にそのような麻の衣服を身につけていた人が、木綿のものを身につけると、なんと柔らかい、なんと肌触りが良い、と感じたことだろうか、という人類の喜びもまた、わかるような気がする。
苧麻というのがどういう植物か、竹富にくるまで見たことがなかった。もちろん本土にもあり、有名なからむし織は苧麻である。苧麻は、まさに草、という感じで、言われなければ雑草が群生しているような感じだ。雨の後などにどんどん伸びてくる。身長158センチの私の胸くらいの丈があり、緑に葉っぱがどんどん出てきて放っておくとふわっと小さな花が咲いてくる。
この苧麻の茎から繊維を取る。茎が茶色っぽくなってくる前に刈り取った方が良いそうだ。カマで根っこの近くから苧麻を刈り取る。刈り取った後、一番上のところを持って片手で茎に沿ってスッと下ろすと、茎についている葉っぱが全部取れる。その後、一番上の葉っぱをとる。茎だけになったものの下の方をぽきっと折ると、外の皮と芯が分かれる。外の皮が折ったところを境に2枚になるのでその2枚の皮を取り、中の芯を取り除く。この皮から繊維を取るのである。苧麻を刈ってどんどんこの茎の皮をとっていく。要するに、この茎から剥いだ上皮から糸が取れるのである。
ある程度貯まったら、茎の皮を纏めてくるっと軽く結んだ状態でバケツの水につける。そんなに長くつける必要はないが、皮につけると柔らかくなる。それを不純物を取り除くために木灰で煮る、と書かれていることもあるし、糸芭蕉の繊維は煮るようなのだが、私が習った方は、苧麻は煮ないで、水につけて晒した後にすぐ、苧引きをしていた。
苧引きは、この皮を金属のヘラ(パイ、と呼ばれている)のようなもので擦っていくことで皮を取り、繊維だけにしていく。親指で支えて金属のヘラを使っていくと親指の内側が擦れて痛いので、スポーツ選手の使うテーピングを使うように勧められた。右の親指にテーピングをして、苧引きをする。
何度も擦っていくと皮が取れて、白く、また美しい青みが残った苧麻の繊維が取れる。これが麻の繊維なのだ。慣れた人なら1分以内で一本の皮から繊維を取れるが、なかなかに力もいるし、こつもいるし、根気もいる作業である。たくさんの苧麻を刈り取って、繊維が取れるのはほんの一握りになるが、こうやって取っていった糸を物干しにかけて乾かす。乾いた苧麻の繊維は白くて誠に美しいものだな、と思う。この状態のものを竹富の神司たちは、神事に使っているという。今はなかなか苧麻を栽培している人がいないので、貴重なものになっているらしい。私に苧引きを教えてくださった方は、たまたまこの繊維を持って船に乗っていたところ、隣に座った方から種子取祭の芸能で苧麻の繊維を使うのだが見つからなくて困っている、と言われ、ああ、そうならここにありますよ、と苧引きした繊維を惜しげもなく差し上げられたそうだ。元々は生活の中にあった苧麻だが、今は探すのが難しくなっているのである。
このようにしてとった苧麻の繊維を糸に績(う)んでいく。苧績みと呼ばれる作業であり、一本ずつの苧麻の繊維を糸にするためにつなげていくのである。こちら、は繊維を取るのにも増して、根気のいる作業である。目でよく見るというよりも、指の感覚で黙々とつなげていく作業なので、元々は、高齢女性の作業、とされていた。苧麻を倒す体力も要らず、織りをするための目の良さもそれほど必要ではないので、高齢になってもいつまでもできる作業であったようだ。縁側に座って黙々と苧績みをする女性の姿は写真でしか見たことがないが、美しい、と思う。年齢によって担当する役割がある、ということにも安らぎを覚える。というか、厳しい時代には、各世代で仕事を分担するしか、なかったのであるが。
さて、11月というのに、また、台風が来そうである。引っ越した2024年は三回台風準備をした。一回目、つまりは私が八重山にやってきて初めての台風は、7月にきた。かなりの大きさの台風で、直撃こそ避けられたものの、台風対策をしてお家にこもっていたが、三、四度停電した。長くて数時間で復旧したが。被害もほとんど出ず、通り過ぎてよかった。二度目の台風は9月の末だった。結婚式で熊本に出かけていたが、台風の進路からして、9月30日には余裕で帰島できると読んでいて、島の人たちも、いやいや、大丈夫でしょう、10月1日くらいまで、船、動くでしょう、とおっしゃっていたが、あっさり9月30日の10時台の便で結構してしまい、四日半ほど船は止まり、五日ほど家に帰れない、ということになった。甘くない。竹富島は離島ターミナルのある石垣島から10分から15分で到着する。距離も5キロほどで近いし、特に危ないところもない海のため、以前は、かなりの風が吹いてもぎりぎりまで竹富便は運行していたらしい。他の離島行きが止まっても、竹富便は動く、という感じだったらしいが、2022年の北海道斜里町のクルーズ船事故の後、全国的に海上保安庁が厳しくなり、いかなる上でも無理な就航は避けるようにということになった、とかで、竹富便も、結構早くから泊まるようになった(と、島の方は言っている)。
ちなみに日本列島の西南端の沖縄県竹富町と、東北端の北海道斜里町は姉妹町である。改めて書いておくと、八重山では、石垣島が石垣市、与那国島が与那国町、その他の島は全て竹富町であり、竹富島のみでなく西表島も小浜島も波照間島も全て竹富町なのである。で、斜里町の「知床国立公園」に長く関わってきた方が「西表石垣国立公園」に関わられることになり、その方を仲介として、国立公園繋がりで姉妹町になって、自然環境整備や保護の交流をしてはどうか、ということになり、昭和48年(1973年)に姉妹町の盟約書をとり交わしたのだという。その後、斜里町の姉妹都市である青森県弘前市も、姉妹の姉妹はまた姉妹、ということで竹富町も弘前市と仲良くし、芸能交流などを盛んに行い、弘前の幻想的なねぷたの行列を竹富島で行ったこともあるという。竹富町役場を勤め上げた方は仕事と芸能交流で、すでに二十回を越えて斜里町に出向いておられるそうで、そこまで行くと、お互い、顔が見えるどころか大変親しい友人となる。東京など経由せず、「辺境同士」の豊かで深いつながりが、東京では想像もできないレベルで進んでいるのである。
で、台風。二度目の台風の後、10月も終わろうとする頃、また、台風が来た。今回は組長級で大きいのではないか、と気合い入れて準備をしていたが、直撃することもなく、また余波も大したことがなくて、船が四日止まっただけ、くらいの程度だった。もう11月になったので台風が来ることもあるまい、と思ったが十日を過ぎてフィリピンの下の方に4個も台風がいっぺんに発生して、そのうち一つがこちらに向かっているという。苧麻はかなり育っていて、苧麻畑の持ち主は石垣在住で、しばらくこちらに来れないので、「刈っておいて」と言われたので、原稿書いていないで、今から苧麻を刈ってくる。
(続く)
 三砂ちづる (みさご・ちづる)
三砂ちづる (みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮育ち。津田塾大学名誉教授、作家。京都薬科大学卒業、ロンドン大学Ph.D.(疫学)。著書に『オニババ化する女たち』『ケアリング・ストーリー』『六〇代は、きものに誘われて』『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』『少女のための性の話』『少女のための海外の話』、訳書にフレイレ『被抑圧者の教育学』、共著に『家で生まれて家で死ぬ』他多数。