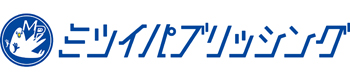- Home
- [Webマガジン]グローバルサウスの片隅で
- 「第5回 キラ」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる
最新記事
10.182024
「第5回 キラ」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる

チベット仏教の国、ブータンは、標高の高いところにある国だから、気温は下がる。いかなる意味でも熱帯の国ではない。ブータン国民は民族衣装をよく着ている、というか、ブータンでは公式の場では、キラとゴという民族衣装を着なければならないことになっている。キラが女性の民族衣装、ゴが男性の民族衣装である。現在のキラは、深くプリーツの入ったタイトスカートのスタイルに、長袖の、体にそうスタイルのブラウスやシャツを合わせていることが多く、それに上着を着たりしている。男性のゴは和服に似ていて、筒袖で対丈、和服と同じように衿を打ち合わせて着て、和服の「おはしょり」と同じように膝の上あたりまでたくしあげて、ケラという帯でとめる。この帯は、日本の帯のように見せる帯ではなく、和服で言えば、おはしょりをとって、留める腰紐のようなものだ。腰紐の用途と同じものがケラなのであって、人に見せるものではない。
そもそも「おはしょり」と言うのは和服の場合は、女性の和服にしか使わないものだ。日本では男性のきものは対丈(ついたけ)で仕立てるので、自分のサイズで作る必要があるから、あまり他人のきものは着られない。女性の場合、「おはしょり」をたくしあげて着るわけだから、少々、丈はあわない他人のきものでも、どうにかして着られる。おはしょりをとる余裕のないきものであれば、対丈で着てしまっても構わない、という融通のきく衣類である。女性のきものは基本的には、「裄(ゆき)」と呼ばれるいわば、袖丈(そでたけ)のみがあっていればあとはなんとかなるのである。少々、身丈が長すぎてもおはしょりでたくしあげてしまえばよいし、前幅、後ろ幅などのサイズが合わなくても、構わない。きものは上半身の背中心さえ合わせれば、腰から下は中心が少々ずれていても構わないので、大体誰のきものでも着られる。裄さえも、気にしさえしなければ、長襦袢の袖が出ないように安全ピンや両面テープでつけたりすればなんとかなるので、要するに女性のきものはよほど背が高い人や恰幅の良い方以外は、大体はなんとか誰のものでも着られることが多い。
この女性のきもののおはしょりには諸説あるようだが、一番よく知られているのは、「妊娠しても着られる」ということだったようだ。おなかが大きくなってもおはしょりの部分があるので、そのまま調整しながら着ることができる。もともと伝統衣装というものは少々太っても痩せても、妊娠末期でも妊娠していない時でも、同じ服が着られるようにできているものが多いから、きものもそういう衣装であった。
で、ブータンの男性の衣装、ゴ、はとてもきものに似ているのだ。衿の打ち合わせもきものと同じだし、おはしょりをとって留めることも、和服と同じである。袖は長くできている。襦袢のような下着としてテュゴと呼ばれる袖の長い白いシャツを着て、そのシャツの袖をゴの袖と一緒に折り返して、袖口に白い部分が出るようにしていて、これはゴの袖口の汚れ防止にもなっていると思う。この発想も、きものの白襟などと同じである。ゴの、前に打ち合わせた部分に、いろいろな荷物を入れることができて、実際ブータンの男性は鞄を持たず、そのいわば「ふところ」になんでも入れて手ぶらで歩いていることが多いらしい。これもきものと似ている。きものを着ていると、ふところや帯の間、女性の場合はお太鼓の後ろ、などいろいろいわば「大きなポケット」のようなところがあり、そこになんでも入れて大体手ぶらで歩けたりする。
20年間きものを着て大学教師をやったのだが、大体、帯の前の部分に、スマホ、クレジットカードなど必要なカード入れと少しのお金を入れ、お太鼓の後ろ、お太鼓部分に日本手拭かハンカチを入れ、ふところにちり紙とかティッシュ(これぞ懐紙、である)とかを入れ、車のキーとか、家のキーとかはやっぱり帯の前の部分に入れて、キーホルダー部分は外に出す、とか、して、暑い時は扇子なども帯に挟んで出かけていた。メモ帳とか、ペンの類も挟むことができるのもいうまでもない。結果としてきものでいると手ぶらで出かけられるので、やっぱりきものがいいな、とか思うのであった。洋服でいて手ぶらで出かけようとすると、今持っている人の多い、カードやお金の入れられるスマホケースを首からかけるか、ウェストベルトのようなものをつけるしかないが、どんな洋服でも合わせられるわけではないので、なかなか手ぶらで出かけることはできない。不便だな、とか思ってしまう。
ブータンの男性は、ゴに黒い長いソックスを合わせて、革靴などを履いている。正式なところに出かけるときは、カムニというショールをたすき掛けにする。これは身分や階級などによって色が決まっているらしいが、2017年に笹川平和財団のプロジェクト・ファインディングで出かけた仕事で保健医療関係の方々に会ったときは、そんなに正式な場ではなかったから、男性はカムニをつけていなかった。この普段着としてのゴは寒いブータンでも大丈夫なように、袷(あわせ)仕立てになっており、さらに生地も、赤や茶色の色合いも、日本の木綿のきものや紬(つむぎ)を思わせるものが多く、なんだか懐かしい感じがする。
女性の民族衣装キラは、ティマと呼ばれる三枚の布を縫い合わせた一枚の大きな布地を斜めに巻き付けてブローチなどで留める、というスタイルが正式なのだそうだ。このティマは男性のゴと同じような絣を思わせる赤や黄色ベースの厚めの木綿で、これがスカートというか、ワンピースのようになる。インドのサリーのような感じだ。この下に、ケンジャと呼んでいるブラウスのようなものをつけて、へちまえりの上着を着る。袖口は、男性のゴで、下のシャツの長い袖を袖口に見せているのと同じ感じで、えりに見えている共布が袖口についている。
2017年、首都ティンプーでは、この一枚布のティマを巻き付けて着ているのは役場の近くで出会った、かなり老齢の女性だけだった。ほとんどのブータン女性たちは、キラを身につけているが、冒頭に書いたように、長いスカートをはいている。これはつまりティマをスカートに仕立てて、着やすく、動きやすくしている、ということなのだと思う。
一枚布を巻き付けただけで、それをスカートにしようと思うと、どうしても動きが制限されてしまう。ブータンのティマはインドのサリーのような感じ、と書いたが、インドのサリーは、サリーの布を巻き付ける下に、長いペチコート様のものをはいている。これは上半身のブラウスと共布で、「見えても良い」ペチコートである。そして、サリーの布をペチコートに挟んで巻いていくのである。だから一枚布で巻いていくが、その下のスカート風のものがあるので結果として動きやすい。インドネシアのサロンなども一枚布を巻き付けるスタイルだが、一枚布を巻き付けてきちっととめると、すごくセンシュアルで格好はいいが、膝がわりにくく、しゃがんで作業などするのは結構大変じゃないかと思う。だからアジアの多くの国では、布を筒形にして巻き付けるタイプに発展していったりしているのではないか、と思う。
現代ブータン女性の多くが身につけているキラは、下は、筒状の布を深いプリーツをつけた状態で仕立てたスカート、上にTシャツやブラウスを着て、その上に、上記のへちまえりの上着を着るスタイルである。ブータンでは公式の場では民族衣装を身につけなければならないことになっているが、おおよその公的な働く場で出会ったブータン女性は、一枚布を巻き付けたティマではなく、仕立てたスカートを履いていた。カジュアルには、このスカートによく売られているTシャツを着て、パーカーのようなものを羽織っている。
ブータンは山の国であり、標高も2000kmくらいのところが多い山岳地帯にある。気温も低く、まあ、一言で言えば、結構寒い。冬には10度を切り、夏は20度をこえるが年間を通じて15度前後の頃が多い。女性のスカートも、東南アジアでよく見かけるような薄い木綿でできているのではなく、しっかりと分厚い木綿でできているのであたたかい。また、スカートの丈が長い。これでは汚れて大変なのではないか、と思うくらい、履いている靴が隠れる床ぎりぎりに仕立ててある。寒いところでは自分の体温をキープすることが大切だから、この床ぎりぎりのスカート丈は、寒さ対応なのであろう。
女性の丈の長い深いプリーツの入ったスカートに、うちあわせのへちまえりの上着の胸元をブローチで留めるスタイルも、また、日本のきものにとても似ている。先に書いたように、男性のゴは丈は短く着るものの、一見して、きものを思わせる。
私は2003年以降、ずっと仕事の場ではきものを着ていて、海外出張にもいつもきものを持って出かけていた。大体の国ではきものは大変目立つ。日本を背負って歩いているようなもので、それも覚悟の上で、着用していたのである。しかし、ブータンできものを着ていても全く目立たない。帯を締めるスタイルとは違うとはいえ、右と左をうちあわせて腰に沿うように下半身を着付け、上もうちあわせて襦袢の襟を見せる、というスタイル自体が、ゴとキラに似ているからである。丈の長さも、きものは裾ぎりぎりに着たりはせず、履きものはしっかりと全部見えるような長さに着付けるので、ブータン女性より短い着付けにはなるものの、ほとんど同じようなスタイルに出来上がってしまう。今もきものを着てブータンの方々と一緒に撮った写真があるのだが、違う衣装だけれども、目立たない、という感じがよくわかる。ブータンの人と日本人は、顔も雰囲気もとても似ていることもあって、まことに目立たないのである。
民族衣装好きなのでブータンでももちろんキラを購入した。ブータンの人がお土産にキラを売っている店を案内してくださったが、そこではキラはスカートに仕立てたタイプと上着、というセットで売られている。というか、スカートと上着は別々に選ぶ。同行していた研究仲間は、そのお店でキラを購入した。金糸などが入っているキラで、いわゆる「よそゆき」なのだと思うが、私が欲しいのは、市井の人たちがみんな仕事に行く時に履いている、黒や赤や黄色の紬っぽい分厚い木綿でできたスカートのキラである。ブータン女性に、それ、どこで買ったの?などと聞きながら案内してもらったのは、市場にある布地屋さんで、そこで布地を選んでウェストとヒップを採寸して縫ってもらった。黒地の紬をおもわせるとても素敵なスカートを仕立て、嬉しくて、ずっとブータンで着ていた。暖かく動きやすく、とても気持ちが良かったが、この裾をほぼ引くような長さはブータンの外では少し着にくくて、カンボジアのサンポットほどには日本の日常では活躍させてやれなかったのが、残念である。
 三砂ちづる (みさご・ちづる)
三砂ちづる (みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮育ち。津田塾大学名誉教授、作家。京都薬科大学卒業、ロンドン大学Ph.D.(疫学)。著書に『オニババ化する女たち』『ケアリング・ストーリー』『六〇代は、きものに誘われて』『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』『少女のための性の話』『少女のための海外の話』、訳書にフレイレ『被抑圧者の教育学』、共著に『家で生まれて家で死ぬ』他多数。