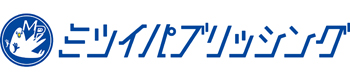- Home
- [Webマガジン]グローバルサウスの片隅で
- 「第16回 スディナ・カカン(前編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる
最新記事
4.42025
「第16回 スディナ・カカン(前編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる

1986年、琉球大学大学院保健学研究科一期生となった。27歳で大学院生になった。大学院生になる、と言うのは、研究生活への第一歩である。大学学部生というのは、学問の世界をのぞき、研究とはこういうものだ、というのを垣間見る機会はたくさんあるのだが、まだ、研究生活に入る、という時期ではない。理科系の学問では3、4年生になると研究室所属などになり、こういうものが研究か、というイメージは持てるようになるものの、本格的な専門教育は、大学院から、ということになっている。
履歴書に学歴、という欄があるが、例えば国連の専門職員応募などでは、もちろん専門職員だからなんらかの専門性があることが求められているわけだが、そこでは学部生以下で専門としたものは、専門と認められない、と言われている。「専門」というのは「大学院」で身につけるもの、と世界的に認識されているので、大学院修士課程、すなわち何でもってマスターの学位をとっているか、で判断されるのである。そういう意味では、学部はなんでも構わない。文学であろうが哲学であろうが、何で修士課程を出ているか、で、仕事の専門性は確認されることになっている。
もっとも修士課程というのは、おおよそ世界中で2年の教育課程である。おおよそどの国でも1年目はその専門科目をいくつかとって学び、2年目に研究を重ねて卒業論文を書く、というプロセスをとっているところがほとんどである。規模は小さくても自らの立てた仮説をもとに、その専門性における理論の組み立て方を学び、その理論的枠組みの中で仮説を検証していくのである。内容によっては1年で取れるものもある。イギリスのマスターオブサイエンス、とよばれる科学の修士課程はTaught courseと呼ばれていて、文字通り「教えられる」ことが中心の修士課程である。こういうコースでは、9カ月間朝から晩までみっちりとその専門についての講義と演習を重ね、最後の3カ月で Dissertationと呼ばれる修士論文を書くことになっている。ともあれ、修士課程というのはそういう研究の作法を知り、論文まで書いてみる、ということをやるのだ。
そして修士課程までは、まだ「研究入門」「研究見習い」「研究手習い」みたいな時期であるから、研究自体にそれほどの独創性は求められていないことが多い。だから簡単に言えば、違う地域で誰かがやったような研究を、異なる地域でやってみた、というような研究でも修士課程なら通用する。手持ちの材料でできることをまとめてみた、というような内容でも大丈夫なことも少なくない。だから、ある意味、修士課程は、入学試験さえ受かれば、誰でも修士号を取得することはできる。「専門性があります」という看板は、だから、志さえ立てて、入学試験に合格するだけの学力を兼ね備え、卒業できるだけの努力ができる人は、割と簡単に掲げられるといえよう。
日本における修士課程の試験は、もちろん文系と理系によって大きな差はあるとはいえ、おおよその試験は「英語」と「面接」が中心で、ある程度の「専門に関する試験」、そして、入試時期によっては「学部時代に書いた論文」が入学試験に反映されるところもある。英語はそして、おおよそは、細かな文法の問題などではなく、専門性に関わる英文和訳と和文英訳、というものが多い。辞書が使える入試も少なくないし、辞書が携帯できなくても、専門性の高い用語は、注釈をつけてくれるところが多いので、おおよその英語力があれば、大学院レベルの入試は突破できるといえよう。
20年間、津田塾大学という東京の23区からかなり離れたところにある小平市に瀟洒なキャンパスを持つ女子大で働いた。2024年秋現在、5000円札の肖像である津田梅子が1900年に、女子の高等教育のために開学した女子英学塾を母体としている大学である。津田梅子は、アメリカのセブンシスターズと呼ばれる7つのリベラル・アーツ・カレッジと呼ばれるレベルの高い小さな7女子大(当時)のうちの一つ、クエーカー教徒の作った、ブリンマー・カレッジを卒業している。リベラル・アーツ・カレッジというのは規模が小さく、専門性追求よりは、学問本来のあり方を学び、広い知識をおさめ、視野の広い人間になることを目的とした大学である。ここを出てから、さらに専門性を追求して別の大学や大学院に進んだり、自らの道を切り開いたりしていくのである。ヒラリー・クリントン、バーバラ・ブッシュ、キャロライン・ケネディなど著名な多くの女性がこのセブンシスターズと呼ばれるリベラル・アーツ・カレッジを卒業している。津田梅子には、このリベラルアーツ・カレッジのイメージが確固としてあったに違いない。日本で学校を作るなら、このような学校、と思ったことであろう。
東京都小平市にある津田塾大学小平キャンパスは1930年に出来上がっており、それはおそらく津田梅子の夢の実現である。ブリティッシュ・コロニアル風の建物が森に囲まれており、アメリカのセブンシスターズと比べるとおそらく規模は比べるべくもないものの、寮も完備され、形は整っている。ここで、権威が嫌いな梅子は自らの理想を積み上げ、教育は学生と教師の間だけにある、と信じていた。校章、校歌、校旗、などシンボリックなものは一切廃し、自らの胸像なども作らせなかった。入学式は、最初に出てみて驚いた。入学式始め、学長挨拶、アルママータ(Alma Mater)斉唱(校歌ではなく、イギリスの古い民謡に津田梅子の盟友アナ・ハーツホンが歌詞をつけた愛唱歌)、終わり、である。あっという間に入学式が終わる。代わりに卒業式は、いまだに卒業生一人一人に学長が卒業証書を渡すので、何時間もかかる。儀礼的なものは限りなく省かれ、学生との関係のみが大切にされているのである。
20年働いてみて、女性の良き未来を願う気持ちの詰まった、誠に良い大学だと思うのだが、今時、東京のはずれの小さな女子大は一般的な高校生の関心からは外れており、受験者は減り続けている。一世代前までは女の東大とも呼ばれ、私学で津田塾を蹴っていくところは早慶しかなかったが、今では立教にも青山にも逃げられる、と古い教員の嘆息を目にしてきた。それでも教育内容は変わらず、入ってきた学生を徹底的に鍛えて、学ぶ人、にしていこうとする方向は変わらない。とりわけ、英語教育については津田梅子の時代から延々と受け継がれる読み書きを基礎とした徹底した教育が行われる。読み書きしかできないから日本人はいつまで経っても英語が話せない、などと言ってはいけない。語学の力は、結局は読み書きの力にかかっている。その土地に生まれた人は毎日話しているから、その言葉は話せるが、論理的、科学的な議論ができて、その言語を使って学問を深められるかというと、それは別の問題である。外国語を使う力がつく、とは、文字通り読み書きの力を伸ばしていくことしかない。そこがしっかりできている人は必要な環境に赴けば、しゃべるくらいはなんなくできるようになる。そこでべらべらしゃべるか、落ち着いて、ゆっくり話すか、はその人のキャラクター次第、ということになる。
レベルの高いと言われている大学でも、英語教育自体についてはそれほど重要視されていないところもあって、入学試験をクリアした入学時の高い英語能力(トップ大学を受験するレベルの英語は相当なものである)をキープすれば良い、という発想もあるのだろう、入学してから大した英語科目はないようだ。津田塾では学科に関わらず、1、2年生では非常に厳しい英語教育を課しているので、まあ、簡単に言えば、1、2年生はいつも英語の宿題に追われて、苦労している。しかし、英語力は必ず入学時よりも上がる。長文の読み書きの力が上がるので、これは、結果として大学院入試に大変有利となる。
津田塾では少人数のゼミを1年次から行うので、自らの興味関心について話すことについても、4年間在籍すると大変よく鍛えられる。はい、5分でこれを話してごらんなさい、と言ったら、それができるようになる(ように教育してきた)。長文の英語の和訳、英訳ができて、自らの言葉で書いた論文について議論できて、面接でも的確に応えることができるので、津田塾から日本の大学院に行こうと思う人は、過去20年の経験でも、だいたいみんな、合格してきた。英語と面接と論文審査、という形の大学院入試に最も強いタイプの人が育ってくるからである。海外の大学院ではそもそも試験はなくて書類審査なので、英文書類でその大学の求めるところと合うような文章を書けるかどうか、で決まるので、そういうことももちろん、得意な人に育ってくるから、こちらもだいたい受かる。ということで、大学を出てからさらに学ぶ方向を探したい、と考える研究者志向の学生には、リベラル・アーツ・カレッジらしい広い学びと、徹底した英語教育が受けられる津田塾はとても向いている学部大学だと思う。(中編に続く)
 三砂ちづる (みさご・ちづる)
三砂ちづる (みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮育ち。津田塾大学名誉教授、作家。京都薬科大学卒業、ロンドン大学Ph.D.(疫学)。著書に『オニババ化する女たち』『ケアリング・ストーリー』『六〇代は、きものに誘われて』『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』『少女のための性の話』『少女のための海外の話』、訳書にフレイレ『被抑圧者の教育学』、共著に『家で生まれて家で死ぬ』他多数。