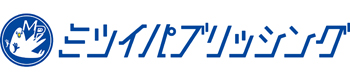- Home
- [Webマガジン]グローバルサウスの片隅で
- 「第13回 ウィピル(中編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる
最新記事
2.222025
「第13回 ウィピル(中編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる

当時、「発展途上国における地域保健」を学ぶものたちにとって、一つのバイブルのような本が、David Wernerの書いた“Helping Heath Workers Learn”という本だった。1970年代から80年代にかけて、国際保健の現場にはプライマリー・ヘルス・ケアという理念が出てきて、医療システムに絡め取られない、自律した健康のありようと、人々のための医療というものが議論されていた時期だった。David Wernerは今も生き生きと読み返される”Where there is no doctor”(医者のいないところで)という本の著者であり、世界中の地方で、医者がいなくてもどのように自分たちの健康を守っていけるのか、ということを考えるバイブルのような本となっていた。発展途上国の僻地、医療システムの届かないところでの健康のあり方を考えると同時に、過剰な医療介入によって自律的な健康自体が損なわれることを感じ始めていた先進国の人間にとっても、示唆の大きな本だった。
プライマリー・ヘルス・ケアという理念の根底には、当時、まだ今のような経済大国ではなかった毛沢東の中国が推進したBarefoot Doctor、“裸足の医者”の成功があった。中国の農村、医者のいないところで、裸足の医者、と言われる簡単な予防医学と簡単な基本的疾患の治療の知識を身につけた村の人を養成することで、中国の疾病死亡率は劇的に下がった、と言われていた。そのような、正規の医療職種ではなく、地元の人が数カ月のトレーニングで担うことができるCommunity Health Worker の育成が国際保健の課題となっていったのが、1980年代だったと言える。“Helping Health Workers Learn”は、そのテキストになった本で、世界中の言葉に訳され、世界中の現場で使われた。そのテキストの表紙は、最も早い時期にCommunity Health Workerの育成が行われたグアテマラの先住民たちの村の写真であり、グアテマラの女性たちは色鮮やかなウィピルを着ていた。だから、ウィピルは自然と、国際保健ワーカーたちにとって、プライマリー・ヘルス・ケアの理念と、コミュニティ・ヘルス・ワーカーの広がりを思い起こさせる、懐かしいものともなっていったのである。
実際に私がグアテマラを訪れる機会があったのは、Chusにウィピルを見せてもらってから10年近く経った、1996年のことだった。ブラジルに住んでいた私は、カトリックの国だから、御法度である妊娠中絶の大規模な調査をしていた。御法度の国だから、その数を把握することは大変困難である。WHO (World Health Organization:世界保健機構)は、妊娠中絶が違法の国で、妊娠中絶のマグニチュード、つまりはことの重大さ、をとらえるための質問票というのを作っていて、私もブラジルでその調査票を使いながら、4000人を超える女性たちをインタビューするような調査を行なっていた。
グアテマラには、INCAPというよく名前の知られた栄養研究所があり、そこはグアテマラの公衆衛生研究の一つの拠点として機能していたようだ。INCAPはあくまで栄養研究所であり、その名をとったインカパリーナという栄養ビスケットはラテンアメリカ中でけっこう有名だった。その研究所が、私が使っていたのと同じ調査法を使って妊娠中絶の調査をする、ということになったらしく、WHOのコンサルタントとしてブラジルからグアテマラに仕事に行くことになった。つまりは調査のアドバイスである。疫学調査は統計の分析が主な仕事のように思われているが、実は、何か解決すべきことがある現場で、研究者が自らのリサーチ・クエスチョンを立ち上げ、それに応えられるような調査をデザインする。そしてその調査がどうすれば最も良いデータが取れるかどうかを、現場で模索していく。質問票を使うが、実際にインタビューするのか、郵送するのか、その場で書いてもらうのか。テーマに従ってどうやってデータをとるのが最もバイアスがかかりにくく、本質に近づけるのかを模索し、現場のデータ収集のインタビューアーたちをトレーニングしていく。研究倫理というものも2000年以降厳しく言われるようになったが、もとより、データを提供してくれる人のプライバシーやその人の思いに寄り添うような調査でなければ、誰も協力してくれないし、答えてくれてもそれは真実に近づく一歩にならないから、倫理的な態度は言わずもがな必要である。そのような研究デザインと研究遂行のロジスティックスの方が、むしろ疫学の真骨頂といえ、統計ソフトを使って分析していくのは、その最後の仕上げのようなものである。
書きながら、これは織物そのものと似ているような気もする。織、というと、高機を使ってトントンと織る光景を想像する人が多いかと思うが、あの経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を織っていく、という作業は織物の最後の仕上げのようなものである。糸を紡ぎ(あるいは紡ぐことは省略しても織るべき糸を選び、用意し)機を用意し、経糸を筬(おさ)に通し、織り機の心臓部とも言える綜絖(そうこう)に糸を通し……と、とにかく織り始めるまでにやらなければいけないことが山ほどあり、むしろその部分に織の本質があるとも言える。織り始めるところに行くまでに、もっともその腕が試されるところがあるのだ。疫学調査も、いわゆる統計分析は最後の楽しみのような部分であるといえよう。
ともあれ、私は1996年にグアテマラに出かけた。グアテマラシティのINCAPで2週間くらい仕事をした。その間の週末に、当時グアテマラで働いていた友人を訪ね、彼女に週末にグアテマラ・シティから連れ出してもらった。友人は山口景子という公衆衛生研究者であり、琉球大学保健学研究科時代の同級生であった。山口さんと私は、この琉球大学保健学研究科の一期生である。復帰前、まだ医学部がなかった頃の琉球大学保健学部は、沖縄の公衆衛生人材育成に大きく貢献してきたところだった。看護師、臨床検査技師、公衆衛生研究者を輩出し、のち医学部保健学科となってからも、医療保健関係で沖縄において重要な役割を果たしてきた。ここが、1986年4月に大学院を創設することになった。私はその経緯を知らないが、おそらく、設置準備のあれこれは結構遅れてぎりぎりだったのではないか。というのは、この設置された保健学研究科の大学院の学生募集が1986年の年が明けてしばらくしてから行われていたからである。それも1月や2月ではない、国立大学の学部生の合格発表が行われる2月末から3月初旬以降のことだったと記憶している。4月から始まる大学院の学生募集を3月にする。その情報が、埼玉県三郷市に住んでいた私に届いたのは、ひとえに新聞のおかげである。琉球大学の保健学研究科一期生募集、この4月から……と書いてある記事が3月に出たのを見つけ、その場で受験を決めたのだ。おそらく内部の方々は、保健学研究科ができるのはわかっていて受験日発表を待っていたのだろうが、当時琉球大学と何の関わりもなかった私にこの情報が届いたのは、今思えば、すごいことだ。
あわただしく受験準備を進め、受験した。専門科目と英語というような受験科目だと思った。すでにアフリカで青年海外協力隊経験を積み、のちにイギリスで苦労することになるとはいえ、当時、私は日本の入試英語程度は扱える自信があったように記憶していて、この試験の英語(大学院の英語だから長文の英文和訳、和文英訳)は平易な問題で、時間を持て余したことだけ覚えている。ほぼ満点の自信があったが、まあ、そんな余裕のある入試は後にも先にもこれしかなかった。とにかく時間もないし、そんな難しい問題を作って選抜する、というような入試でもなかったのかもしれない。
私は崎原盛造先生という米留帰りの保健社会学研究室に所属することになった。沖縄では米留帰り、で通用するが、少し説明が必要だろう。戦後のアメリカ統治時代、アメリカは多くの沖縄の研究者の卵、というか、優秀な人材をアメリカに留学させて学位をとらせ、沖縄に戻らせる、ということを、まあ、植民者らしい態度で行なっていて、数多の優秀な沖縄の若者が海を渡った。聞くところによると、軍の飛行機でアメリカまで運ばれた、ということである。当然のことながら、英語は堪能、米国事情にも通じ、米国人の友人も多い、米国贔屓の研究者を大勢育てた。崎原先生はそのようにして米国で保健社会学の学位まで取って帰国された方だった。
(後編につづく)
 三砂ちづる (みさご・ちづる)
三砂ちづる (みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮育ち。津田塾大学名誉教授、作家。京都薬科大学卒業、ロンドン大学Ph.D.(疫学)。著書に『オニババ化する女たち』『ケアリング・ストーリー』『六〇代は、きものに誘われて』『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』『少女のための性の話』『少女のための海外の話』、訳書にフレイレ『被抑圧者の教育学』、共著に『家で生まれて家で死ぬ』他多数。