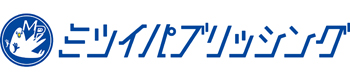- Home
- [Webマガジン]グローバルサウスの片隅で
- 「第12回 ウィピル(前編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる
最新記事
2.72025
「第12回 ウィピル(前編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる

ウィピルがつないでくれたご縁だなあ、と思った。ウィピルはグアテマラの民族衣装の上衣である。グアテマラの織物で出来上がった美しいウィピルは、頭を入れる穴はついているが、まっすぐに織った布の、脇を真っ直ぐに縫ってブラウスにするので、脇が縫っていない状態だと、そのまままっすぐタペストリーのようにかけることができる。20年勤めた大学の研究室には、このウィピルを本棚の上にかけていて、数知れぬ人に美しいですね、といってもらっていた。
2024年3月、20年を過ごした大学を離れ、竹富島に移住することにした。研究室の片付けは、今も焦って、わあ、部屋の片付けができていない、という夢を見てしまうくらい大変なことだったのだが、なんとか終わった。九割以上のものを処分してきたが、2枚のウィピルと、コルテと呼ばれるウィピルに合わせる腰巻きスカートになる一枚布だけはさすがに処分することができず、竹富島に持ってきていた。
竹富島は美しい海と空、準美観地区に指定された街並み、そこを行く水牛車……などで知られているが、元々は「民藝と伝統芸能の島」だった。いや、過去形ではない、伝統芸能は今も盛んで、最も大きな祭りである種子取祭(第11回参照)は国の重要無形文化財に指定されているし、伝統祭祀は一年を通じて、ある。
今では沖縄を代表する柄行きとなっている「いつの世までも一緒に」という「五」と「四」の四角が意匠となったミンサー織は、もともと竹富のものだった。ミンサー織も、芭蕉布も、八重山上布も、島の日常として織られており、1950年代に島にやってきた柳宗悦に始まる「民藝運動」の面々や、バーナード・リーチは竹富島のありように感嘆した、と言われている。今も「竹富民藝館」はあり、竹富町織物協同組合も竹富島にあるのだが、織り手も限られていて、生活の中に織りはもう生きていない。島に移住する前から、この島の織りの伝統に寄り添っていきたいと思っていたし、高機(たかばた)を使うようになる前の、地機(じばた)と呼ばれる腰を使う織り方にも興味を持っていた。
移住して四カ月ほど経った頃、西表島で「アンデスの糸紡ぎとミサンガ作り」のワークショップが行われる、という知らせが入ってきた。人がもともと使っていた繊維は麻であると言われている。麻から繊維をとって布にする。竹富島でも、もともと島で作られていた布は島に自生する苧麻や糸芭蕉を使って作る八重山上布や芭蕉布であった。
今や、八重山上布も芭蕉布もとんでもない高級着物になっているが、2024年現在、80代になるくらい以上の方々が子どもの頃は、子どもたちも皆、島で作った芭蕉布を身につけていたという。芭蕉布のパンツはゴワゴワして肌触りが悪かったというが、さもありなん。芭蕉布のズボンを履いて中学校に行った、というが、今思えば大変贅沢な話である。苧麻や糸芭蕉から糸をとるのはなかなか大変である。例えば苧麻も切り倒した後、干して、水につけ、それを金属のヘラ様のものでしごいて繊維を取る、苧引き(うーびき)という作業をする。それを乾かして、一本の糸につなげていく。この作業を苧績み(うーうみ)、といい、根気がいる作業で、島では高齢女性の仕事であったという。
そのようにして糸というものは作るものだったところに、木綿が入ってくる。麻の、通気性は良くて丈夫なものの、肌触りが今ひとつよくなくて、糸にするのも大変、という素材と格闘していた人類に、木綿がもたらされる幸せは、何度でも追体験できるような気がする。ふんわりとした肌触りは一度経験すると忘れ難い。それに、綿、という植物は花が咲いて綿の実ができるが、その綿の実からすぐに糸をとって紡ぐことができるのだ。苧麻のことを考えると、その工程のシンプルさには感動してしまう。
ぽん、とできた綿の実から、まず、綿繰り機でタネを取る。タネをとったら、綿打ち弓の振動で綿の線維をからませてほぐしていくか、カーダーなどでほぐしていく。ほぐしてふわふわになったら、それを糸車で糸にする。麻と比べるとあっという間に糸ができて、あっという間に肌触りのよい布になる、ということに人類は感動したであろう。さらにお蚕などは糸を最初から吐いてくれるのだから、これまた、絹とは素晴らしい織物なのだが……。とにかく、麻しかなかったところに、綿が入ってくると、それは大きな感動を伴ったことだろう。
とはいえ、この綿繰り機とか綿打ち弓とか、糸車、はそれなりに場所もとるしインフラ整備も楽ではない。はい、綿の実ができました、では糸にしていきましょう、というわけにはいかないのである。西表島で行われたワークショップでは、道具を使わなかった。アンデスの人たちがずっとやってきているように、小枝だけで糸を紡ぐ。教えてくださったのは、キリム織りやグアテマラの織りなど、古代から伝わる染織技法を研究し、織り手として活動したり教えたりしておられるKoyun由紀子さんである。
棉を育ててみたいな、と思って、やってみると、できるんですよ、プランターとかでもね。綿の実がぱかっとはじけてそれを摘む。そして糸を紡ごうとしても、簡易とはいえ、工程ごとに道具が必要だから大変ですよね、綿繰り機も綿打ち弓も、糸車も。綿をとりました、はい、糸に紡ぎました、というわけにはいかない。道具を使わなくてもできる、というやり方はやはりすごいと思います……と穏やかな口調で語っておられた。使うものは枝一本。もちろん、糸車よりずっと時間のかかる作業であるが、道具が何もいらない。まさに魔法の糸つむぎ、なのであった。
グアテマラの女性たちの美しい織にはじめてふれたのは、30歳になる少し前、ロンドンに行った時のことだった。国際保健医療の分野で仕事をしたかった私は、ロンドン大学熱帯医学院の「開発途上国における地域保健」という修士課程に入学した。1年間のコースに参加するのは、25カ国から来た32名の現場の経験豊富な医療関係者たちで、この1年はまさに私の人生を変えたし、そこでの出会いは今も私の人生の道標となっている。25カ国、は、思いつくだけでも、イギリス、ジンバブエ、ソマリア、ガーナ、インド、フィリピン、カナダ、アイルランド、ヨルダン、台湾、タイ、ミャンマー、ブラジル、コロンビア、ペルー、ドイツ、オランダ、ニュージーランド、イエメン、バングラデシュ、スペイン、日本……。
このコースの仲間で、グアテマラと革命後のニカラグアで働いていた、スペイン人のチュスとは大学の狭い寮の部屋も共有し、無二の親友となった。Chus、という名前はスペイン人でもそんなによくある名前ではなく、愛称である。彼女の本名はMaria Jesus、スペイン語ではマリア・へスース といい、日本語に直すとマリア・イエス、だから、まことにクリスチャンらしい名前である。で、彼女曰く「Maria Jesusなんてね、街中山ほどいるのよ。小さい頃、Jesusとうまく言えなくて、へスース、ヘチュース、チュス……みたいになって、それからずっとChusと呼ばれているの」と言っていた。私の名前はChizuruチヅル、であって、ChusもChizuruも多くの国の人(なんと言っても25カ国から来ているのだから)には覚えにくく、発音しにくい。クラスメートの多くは結構私たちの名前(外見はスペイン人と日本人だから全然似ていない)を混同し、えっと、君はChusだっけ、Chizuruだっけ、とよく言われた。ウィピルを最初に見せてくれたのは、彼女だったのである。グアテマラの先住民たちが、自分たちで織り、村ごとに異なるデザインのウィピルを着ていて、母から娘に伝承される。現地の人はその柄行を見るだけでどこの人かがわかる、と言われていた。今はかなり変わってきているようだが、35年前は間違いなくそうだった。Chusの見せてくれた、白地に赤い模様のあしらわれたウィピルは本当に素敵だった。
(中編につづく)
 三砂ちづる (みさご・ちづる)
三砂ちづる (みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮育ち。津田塾大学名誉教授、作家。京都薬科大学卒業、ロンドン大学Ph.D.(疫学)。著書に『オニババ化する女たち』『ケアリング・ストーリー』『六〇代は、きものに誘われて』『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』『少女のための性の話』『少女のための海外の話』、訳書にフレイレ『被抑圧者の教育学』、共著に『家で生まれて家で死ぬ』他多数。