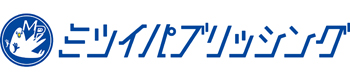- Home
- [Webマガジン]ダブリンつれづれ
- 「第23回 ベルファストの赤い手」ダブリンつれづれ / 津川エリコ
最新記事
2.142025
「第23回 ベルファストの赤い手」ダブリンつれづれ / 津川エリコ

ダブリン発、英国領北アイルランドの首都ベルファスト行きの電車は二時間ちょっとである。植民地時代、ベルファストはアイルランド経済の中心だった。英国が手放さなかった理由である。独立をめぐって英国との条約調停に臨んだアイルランド代表は、すでに三年近く続いていた独立戦争の犠牲者を増やさないために、英国の条件を飲み妥協した。真の独立へ向かってのとりあえずの第一歩ということであった。
ベルファストには英国が強く拘った非常に重要な二つの産業があった。一つは世界有数の造船会社、ハーランド・アンド・ウルフ(以下H&W)であり、二つ目は紡績産業だった。H&Wの二つの巨大なクレーンは、旧約聖書に登場する怪力のサムソンと巨人のゴリアテに因んで名づけられた。今日でもサムソンとゴリアテは、遠くから目に付くベルファスト繁栄の象徴である。
この象徴には裏面もある。英国系プロテスタントによるアイルランド系カトリック差別と両者の対立の象徴である。北アイルランドではアイルランド系カトリック教徒に対する様々な差別があったが、雇用面での差別が最も深刻であった。最盛期には三万五千人を雇用し、文字通りベルファストを潤わせたH&Wに、カトリック教徒が就職することは非常に難しかった。氷河に衝突して沈没した豪華客船タイタニックもここで製造されている。タイタニックの三等客室は、アメリカへ移住するアイルランド人で溢れていた。
二つの目の産業、紡績業は、十七世紀にフランスで迫害されアイルランドに移住してきたユグノー派と呼ばれる新教徒が始めた、麻の栽培が発端となった。アイリッシュリネンは、大英帝国の拡大によって需要が高まり、質の良さもあって世界中に知られるようになった。
造船と紡績、この二つの大きな産業は航空機と化繊の開発によって廃れた。廃れた産業、続く内紛。英国にとって、北アイルランドは厄介なお荷物の存在になった。手放したい。ただし、アルスターとも呼ばれる北部地方にはスコットランドからの移民が多く、彼らは英国人であり続けたいと主張し英国がそれを無視することは難しい。
私が初めてベルファストの駅に降りたのは、八〇年代末である。別の目的地へ行くための経由駅だった。乗り換えの電車が出るまで三時間以上もあったので、私はベルファスト市内を見学することにした。スーツケースをロッカーに入れようと探した。ロッカーがない。駅員さんに「ロッカーまたは一時預かり所がありますか」と訊ねた。ところがどちらもないという。困ってしまった。すると彼が「僕が預かってあげるよ」と言った。好意に甘えてそうさせてもらった。三時間して帰ってくると、彼が改札口で私のスーツケースに跨っていた。
私は日本で北アイルランド紛争関係の本を読んでいたが、ただ読んでいたというだけで何も理解していなかったことに気付いた。イギリス・プロテスタントとアイルランド・カトリックとの紛争は続いていたのだ。双方に穏健派と強硬派があり、一つではない強硬派は武装もした。ロッカーや一時預かり所が無差別テロの格好の場所になることは、火を見るよりも明らかだった。
それからから何年経っていただろう。アイルランドで公認ツアーガイドの資格を取っていた私は、日本からのツアーグループを伴って北アイルランドのデリー市(プロテスタントはロンドンデリーと呼ぶ)でウオーキングツアーをすることになった。一九九八年、和平が成り立ち、アイルランドツアーに北アイルランドが含まれるようになった初期の頃である。地理に不案内な私はデリー市のツーリストインフォメーションに助けを求め、職員のトムさんがついてくれることになった。説明は私がするつもりでいたが、ツアーが始まるとトムさんが全面的にリードし、私は通訳になった。
私は気付いた。道行くデリーの人達が、東洋からの観光客を見て立ち止まったり振り返ったりして眺めるのに。人々の半ば微笑んだ表情が語っていたのは、観光客が来るということに、紛争が終わった証拠を見出していたのだろう。
紛争時代を生きたトムさんの説明には、真実の思いが籠っていた。予期していなかったが、トムさんの解説は、イギリス領に住むカトリック教徒のアイルランド人としての観点からだった。彼はある慰霊碑の前で立ち止まった。一九七二年にアイルランド系の公民権運動グループが「インターンメント」(逮捕状なしで逮捕、拘禁できる)の導入に反対するデモを起こしたとき、カトリック系デリー市民がイギリス軍の兵士によって銃撃され、十三人が死亡した事件が起きた。翌日、ダブリンでは怒った二万人の市民が英国大使館に押しかけ、大使館を焼き討ちにした。アメリカでは、アイルランド系の上院議員、エドワード・ケネディが英国を公然と非難した。トムさんが立ち止まった慰霊碑には、事件の後に亡くなった一人を加えて十四人の名が刻まれている。アイルランドを代表するロックグループU2のヒット曲「ブラディ・サンデー(Sunday Bloody Sunday)」は、この事件を歌ったものだ。
双方が歩み寄っての和平はカトリック系、プロテスタント系双方の強硬派が武装解除をし、選挙による共同統治ということで一致した。その年、双方の最大政党の党首、ジョン・ヒュームと、デイヴィッド・トリンブルの二人がノーベル平和賞を分け合った。U2のボーカル、ボノも授賞式の壇上に上がり二人の手を取ったのが、印象的だった。
古代アイルランドには五つの王国があった。北部アルスターはその一つである。それに基づいて今は、四つの地方に分かれている。行政区分としての機能はないが、文化的、歴史的な意味から今でも使われていて、それぞれに紋章が決まっている。北部アルスターの紋章は「赤い手」である。キリスト教が入ってくる以前の民話伝説に由来しており、よく知られているバーションは次のような話である。アルスターに王の後継者がいなかった時、湖をボートで対岸に渡る競争をし、最初に「アルスターの石」に触れたものが王の後継者となる、ということになった。「アルスターの石」は王の就任式が行われてきた石である。競争に負けそうになったある若者が、自分の手を切り落として石に向かって放り投げ、競争に勝ちやがて王になった。赤い手はこの劇的な場面に由来する。
赤い手のシンボルは様々に使われてきたが、北アイルランドの分離以来、プロテスタントが使うようになった。植民地は血を流して奪った側のものだ、ということだろうか。ベルファストの住宅街の切妻に突然現れる壁画の巨大な赤い手を見た人は誰でも、「あれは一体何だろう」と一瞬たじろぐに違いない。「赤い手」に対抗するカトリック側の壁画の代表的なものは、刑務所でハンガーストライキを実行して死んだボビー・サンズだろう。十人の若者が政治犯としての扱いを要求して、次々と自分を餓死させた。ボビーは最初の一人である。
ベルファストだけでもこうした政治主張のある壁画がおおよそ三百もある。ナチのカギ十字はナチがシンボルとして使う数千年前から、吉祥の印として存在したということであるが、今では不気味なものとして目に映る。「アルスターの赤い手」と呼ばれる紋章は一人の若者が流した血であるが、紛争で多くの市民の血が流された歴史の後では、やはり不吉に見える。
北アイルランドでは紛争のため、長い間、家の値段がとても安かった。ベルファストでも和平以前は、赤レンガの瀟洒な家がいくつも空き家になっていた。家の値段も安かったが、歯の治療費も安かったので、紛争のある頃でも私は歯の治療のために何度かベルファストへ行っていた。ダブリンからわざわざ二時間もかけて行くせいか、治療時間を長く取り、二回ぐらいで治療が完結するようにしてくれた。
目下、北アイルランド自治政府の首相は、南のアイルランド共和国との統一を目指すシン・フェイン党に属している。国民投票によって北アイルランドが共和国に戻ってくるという可能性がないわけではない。私が生きているうちにそれが起こるだろうか。
参考文献:
鈴木良平『IRAアイルランド共和国軍』彩流社、1988年。
Holland & Wolfe Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Harland_%26_Wolff
ホロコースト百科事典「カギ十字(スワスティカ)の歴史」 https://encyclopedia.ushmm.org/content/ja/article/history-of-the-swastika
Sean McMahon, A brief History of Northern Ireland, Brehon Press Ltd, 2011.
Eamonn McCann, Maureen Shiels, Bridie Hannigan, Bloody Sunday in Derry: What Really Happened, Brandon Books, 1992.
津川エリコ
北海道釧路市生まれ。ダブリン在住。『雨の合間』(デザインエッグ)で第55回小熊秀雄賞受賞。小説「オニ」(『北の文学2022』所収、北海道新聞社)で北海道新聞文学賞受賞。著書に詩集『アイルランドの風の花嫁』(金星堂)、随筆集『病む木』(デザインエッグ)があるほか、詩集アンソロジー”Landing Places”, “Writing Home”, “Local Wonders”(いずれもDedalus Press)に作品所収。