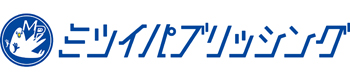- Home
- [Webマガジン]グローバルサウスの片隅で
- 「第14回 ウィピル(後編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる
最新記事
3.82025
「第14回 ウィピル(後編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる

琉球大学に来る前に、ザンビアで青年海外協力隊活動をしていたことがある。そこに、まだまだ草分けの分野であった生態人類学を専門分野とする故・掛谷誠氏と、杉谷祐子氏が調査に来ていた。杉山さんは私とほぼ同じ年代、初めてのアフリカのフィールドワークで気が合ったこともあり、よく一緒に過ごした。
琉球大学大学院に進む時、杉山さんが「私たちの仲間がたくさんいるから」と紹介してくれたのが、当時の保健学研究科生態人類学講座の加納隆至教授、武田淳助手、伊谷原一研究員、そして、私の所属した保健社会学講座の佐藤弘明助手、だった。今西錦司をルーツとして、伊谷純一郎らによって基礎づくりをされた生態人類学は、サルを相手とするグループと、ヒトを相手とするグループに分かれていく。加納氏は、保健学研究科ができた1980年代、すでに大型類人猿ボノボの研究者として世界的に知られた人だった。伊谷純一郎氏の長男、伊谷原一氏は、彼のもとでいわば修行中の研究者、のち、彼もボノボの世界的な研究者となり、京都大学野生動物研究センターを率いる存在となっていく。武田淳氏はトーゴやマリ、佐藤弘明氏はカメルーンなどをフィールドとする、ヒトを対象とする生態人類学者だった。
私は、保健社会学教室で公衆衛生の実地調査を学ぶこととなるが、最初に出たフィールドは、佐藤氏とともに出かけた多良間島や大宜味村であった。研究者として第一歩を踏み出した時に、周囲に卓抜したフィールドワーカーである生態人類学者の皆様がおられたことは、私のその後の疫学研究にも大きな影響を与えている。
ともあれ、私は保健社会学教室の大学院生一期生となった。ザンビアで会った杉山さんは、スタッフのみでなく、同級生となる大学院生にも知り合いがいて、生態人類学教室で大学院一期生となる山口景子さんを紹介してくれたのである。彼女は西表島をフィールドとする生態人類学者であり、結果として私の人生に大きな影響を与える人となった。
当時、琉球大学には八重山芸能研究会という八重山地方の郷土芸能を取材して、舞台にあげる、という大学の部活としてはハイブローな民俗学的活動をしているサークルがあって、西表島をフィールドとする山口さんは、フィールドにより近づきたいという下心、というと失礼な言い方だが、そういう研究熱心さもあって、このサークルに入れてくれ、と言いにいくことにした。で、ひとりではこころもとないので、私を引っ張っていったのだ。私は当時、八重山芸能はおろか、沖縄民謡についてもほとんど何も知らなかった。しかし、八重山の民謡、踊りに自らの土着を呼び覚まされ、心をわしづかみにされ、その後数十年、舞扇と音源を携えて世界を回ることになり、40年近く経った頃、この八重山芸能研究会のつながりをきっかけとして、八重山竹富島に家を建てて移住してしまうことになるのだから、人生というのは、何が起こるかわからない。あの時、山口さんが私を八重山芸能研究会の活動に引っ張っていかなければ、今、竹富島で暮らしている私は、いない。
1996年、WHOコンサルとしてグアテマラを訪れたとき、その山口さんは、グアテマラでシャーガス病に関するJICA (Japan International Cooperation Agency:日本国際機構)の長期専門家をしていた。お互い仕事のない週末、彼女は私をアンティグア、というその名も「古い」という街に連れて行ってくれた。週末には、民族衣装の市が立つという。そこに出かけて、ウィピルを買った。白地に濃い色がびっしりと縫い込まれ、私はこれは刺繍だと信じて疑わなかったが、のちに、これは織りである、と知る。これが、私の人生最初のウィピルであった。着てはいないが、ずっと手元に携えることになる。
1990年代ほとんど全てをブラジルで過ごしたが、2000年に帰国し、2001年1月1日付で厚生省(当時)の国立公衆衛生院疫学部に就職する。ロンドン大学で疫学のPhDをとり、フィールド経験も豊富で、英語の論文をたくさん発表していた私は、なんだかするすると国家公務員の研究者になれたのだが、時代が変わっていくきっさきにいた幸運だったのだと思う。それより前は、医学部卒か有名国立大学の博士でもとっていないとこういう研究所に入ることは不可能で、海外で15年も暮らして、何をやっていたのかわからない人間に国立研究所のポストとか、なかったと思うが、当時は「科学的根拠に根ざした医療(Evidence Based Medicine:EBM)」などが取り沙汰されている時期でもあり、海外で学位を取っていて英語もできて仕事もできそうなら、まあ、いいか、みたいな感じで取ってもらえたのだ。当時の疫学部長と院長には、今も感謝している。
当時の国立公衆衛生院は港区白金台にあり、ロックフェラー財団が建てた非常に重厚な建物だった。映画のロケなどにもよく使われていたようで、作り込まれた講堂や、どっしりとした階段の佇まいは、本当に素晴らしく、ここに仕事を得られて嬉しいと思うような場所だったのだが、あっけなく一年半後、埼玉県和光市に国立保健医療科学院、という何をやっているかわからないような名前の研究所になって、移転してしまう。国立公衆衛生院、のち、国立保健医療科学院は厚生労働省の教育機関でもあり、文科省の学位ではないが、ディプロマ、修士、博士などの学位を出して、そのための教育も行なっていた。研究所員は、そういった学生たちの教育も担う。もともと国立公衆衛生院は保健所長をはじめとする保健所関係者の研修先でもあり、修士、博士を目指す学生さんもほとんどは医師、看護師、助産師などの医療関係者だった。現在は各都道府県に看護大学が存在するが、まだ、看護婦養成のほとんどを専門学校が担っていた頃は、必要な学位を公衆衛生院でとって、看護学校で教える方も少なくなかったという。
国立保健医療科学院として和光に移転した後の修士課程におられた笹川恵美さんという助産師さんは、国際保健志向の方で、すでにメキシコで助産師としての青年海外協力隊活動を経験されていた。その後もこの国際保健の分野での活躍を目指し、JICAからの援助も受けて、フィールドワークや現地活動の経験を重ねていたのだ。そんな彼女が、JICAからの研修先として指定されたのがグアテマラで、リュックを背負って緊張しつつも張り切って数カ月の研修に出掛けて行ったのを覚えている。
JICAの研修先はケサルテナンゴというところで、そこで、笹川さんが私にお土産に持って帰ってくれたのが2枚目のウィピル、さらに、スカートとして使う織りの腰巻き布コルテ、ベルトに使うファハである。こちらのウィピルは白地にバラの模様などが織り込まれて、さらに刺繍が施されてあるものだった。見るからに清楚で美しく、こちらのウィピルは、国立保健医療科学院から2004年に津田塾大学に異動してから20年間、一貫して研究室の本棚のカーテンがわり、という壁掛けのように飾って使っていた。これは本当に素敵ですね、どこのものですか、と、何人に聞かれたか数えきれない。その度に、これはウィピルというグアテマラのブラウスであることを説明していた。
その後、国際協力の仕事としてかなりディープに関わってきた「出産のヒューマニゼーション」という女性の身体性と、生まれてくる赤ちゃんの力を十二分に生かす、という分野のプロジェクトを上記の笹川恵美助産師がエルサルバドルで立ち上げ、5年以上、エルサルバドルには毎年のように通うことになったが、その後、グアテマラには赴く機会がなかった。
初めてグアテマラのウィピルを見て、グアテマラのあれこれについて聞くようになった1980年代は、まだ国内に内戦の厳しさが色濃くある頃でもあり、先住民の村では内戦の影響で、上記のコミュニティ・ヘルス・ワーカーが殺されたり、反政府運動の拠点になっている、とJICAの青年海外協力隊は入れなかったりしたことがあるようだ。ウィピル自体も、以前は、着ているウィピルで出身の村が特定できるほど特徴のあるものだったのだが、その後、若い女性たちは自分たちの好きな柄があれば、そのようなウィピルを着るようにもなったと聞いたし、青い色を中心とする、流行りすたりもあるようだった。そういう話は聞くが、私はグアテマラに特にそれからご縁を持たずに、時間が過ぎた。
数十年後に出会ったのが、この西表島でのKoyun由紀子さんのワークショップであり、グアテマラの織りと糸つむぎ、だったのである。グアテマラの織りに詳しい由紀子さんは、私の持っている2枚のウイピルのうち、笹川さんの買ってきてくれたバラ模様のウィピルはケサルテナンゴのシェラという村のもの、もう一枚の、私自身がグアテマラに行った時、アンチグアで求めたのはチュアランチョという村のもの、と教えてくださった。
西表島のワークショップを経て、由紀子さんとは今、竹富島でのワークショップを始めている。ウイピルがつないでくれたご縁、そのものである。今後の展開が本当に楽しみだ。
 三砂ちづる (みさご・ちづる)
三砂ちづる (みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮育ち。津田塾大学名誉教授、作家。京都薬科大学卒業、ロンドン大学Ph.D.(疫学)。著書に『オニババ化する女たち』『ケアリング・ストーリー』『六〇代は、きものに誘われて』『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』『少女のための性の話』『少女のための海外の話』、訳書にフレイレ『被抑圧者の教育学』、共著に『家で生まれて家で死ぬ』他多数。