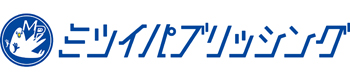- Home
- [Webマガジン]グローバルサウスの片隅で
- 「第22回 小浜節」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる
最新記事
7.52025
「第22回 小浜節」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる

クモーブシ、と発音する。小浜島の民謡である。内地で八重山民謡に興味を持って習い始めるとき、何が弾けるようになりたいか、と聞いたり、長く習ってきた人にも、どの曲が好きか、とか聞いたら、小浜節、という方が多いのだそうである。もちろん八重山でも広く愛されている。ゆっくりとした二揚げ(三線の本調子から二の弦〔中弦〕を揚げる)の曲で、初心者がまず弾く曲ではない。八重山では、初心者は赤馬節(あかんまぶし)とか鷲ぬ鳥節(ばすぃぬとぅるぶし)などを練習し、そのあと、デンサ節、鳩間節(はとぅまぶし)、などを弾いていくのだと思うが、小浜節は、もうちょっと節回しも難しいようなので、八重山民謡を習って憧れをもつ曲の一つのようだ。いうまでもなく八重山諸島のうちのひとつ小浜島の民謡であり、結願祭で唄い踊られる。小浜島は、一世を風靡した感のあるNHK朝の連続テレビドラマ「ちゅらさん」の舞台でもあったことで知られている。八重山民謡の中でも特に愛される唄であることから、小浜節大会もすでに15回くらい開かれている。
踊りは、小浜の結願祭で踊られるのと同様の、白いカカンと黒に赤いトリミングをほどこしたスディナに、赤いサジ(手拭い)を額に巻く。四つ竹を打ちながら踊る、ゆったりした動きの女踊りである。余韻の残る美しい踊りだ。民謡そのものであるが、踊りにもファンが多い。演目としても魅力のあるものなのである。
その小浜節をとつぜん踊ることになった。石垣市民会館中ホール、“郷土芸能の夕べ”である。この催しは、八重山の八重山舞踊研究所などがまわりもちで、金曜日の夜8時から1時間以内の公演をおこなう、もともと観光客向けに設定されたものであるという。チケットも500円(2025年4月から1000円に値上がりするらしいが)と手頃であり、舞踊研究所で踊りを習う者にとっては場数を踏む貴重な機会になっている。2024年(令和6年)度のさいごの公演は3月21日であり、荻堂久子八重山民俗舞踊研究所が担当になっていた。荻堂久子氏は舞踊研究所を率いる方だが、島言葉普及にも尽力されており、沖縄県の高齢者による意見発表大会のようなところで優勝したりなさっているし、また、石垣島の大阿母御嶽(ホールザーオン)のツカサでもある。頭上運搬の研究やツカサの聞き取りをしているころ、山里純一氏の紹介により荻堂久子さんを紹介されていて、そのおりに稽古着も購入して入門していた。2019年ごろのことであるが、そのあと新型コロナパンデミックが始まり、人の行き交いが制限されるようになったため、実際にはほとんどお稽古に通うことはできなかった。
その後、2024年4月に八重山竹富島に移住する。八重山毎日新聞に二度ほど、東京通信員である竹富島出身の有田静人さんが私の移住に関わる記事を書いてくださったから、私が竹富島に移住することは島で新聞を読んでいる人は皆知っていたし、なにより60代以上の方々は八重山毎日新聞を読んでいるから、私の移住は八重山全域に知れ渡った。というか、そのために記事を書いてくださったのだ。荻堂先生はその度に電話をくださっていたから、私の移住はご存じだった。
実際に島に移住すると、結構毎日あれこれあるし、生活を建てて行き、周囲に馴染み、やってくるお客さんに対応しているだけで過ぎてゆく。石垣島には確かに買い物や歯医者や耳鼻科に通うために行くのだが、それだけで帰ってきてしまうことになり、石垣にお住まいの方々にはご無沙汰をしたまま一年が経ちそうになっていた。八重山舞踊研究所を率いておられる荻堂久子先生のところにもご挨拶に行きたいし、踊りの稽古も再開したいし……と思っていたが時間が過ぎていた。
親しくしている石垣島出身の亀井道子さんは、石垣島方言、シマムニの会を率いておられ、絵本を出版したりさまざまな賞を受賞されたりしている。荻堂先生もシマムニ普及の活動をなさっているから、お二人は知り合いであり、2025年2月23日に石垣市平得公民館で「シマムニカルタ」を作るためのチャリティー公演が行われ、平得老人会会長でもある荻堂先生中心に芸能公演をされるという。荻堂先生にご挨拶する良い機会だと思って、道子さんに平得公民館に連れて行ってもらった。楽屋から出てきてくださった荻堂先生は私の顔を見るなり、「あっ、3月21日の郷土芸能の夕べに出てね!」とおっしゃる。まあまあ、とその時はお忙しくしておられたから、右から左に流していたが、1週間後に電話がかかってきた。なんでも当てにしていた方が一人出られなくなったので、赤馬節の女踊りの役と小浜節を踊ってほしいと言われた。大変なことだと思えど、愛すべき小浜節、さらに憧れていたスディナ・カカンに四つ竹の踊りである。断る理由がない。電話がかかってきた翌日から荻堂先生の稽古場に通い始めた。3月21日まで3週間、ない。
実際には大変である。女踊りを初めて習うし、手が覚えられないし、三人で踊る踊りなのだが、すでに踊りを習得して息もあっている二人について行かねばならないし。今日はがんばろうと思うが次の日には、もう無理だ、これは踊れない、と思って落ち込み、また翌日はいやいやなんとかなる、これは憧れの体現だ、がんばろうと思う、というような日々を繰り返す。
あまりに長いこときちんとやっていなくて、踊りを覚えるとはどういうことだったかを思いおこす。唄は踊り、踊りは唄、であり唄を覚え、唄が自分の一部になって、初めて踊れると思う。音を聞いて踊り出したいのが、踊りだから。音を聞いて思わず体が動いて、それに合わせて動く。そういう人間の基本的な喜びのあらわれが踊りなのだ。世界中でそういう動きや踊りを見るたびに感激する。踊りというのは習ってやるものだ、という意識がどうしてもあったが、沖縄の方が沖縄の民謡がかかるとすぐに体が動き出す、という、あれこそが基本だ。
今も忘れられないでいることがある。25歳の時青年海外協力隊に参加した。1983年の末頃のことだ。当時は東京の広尾で一ヶ月研修をした後、長野県駒ヶ根で二ヶ月の語学研修を受けることになっていた。任地別に言語が決まり、私の赴任地は現地の言葉があまりに多様であることから、植民地時代の公用語であった英語をそのまま公用語に使っている南部アフリカの国ザンビアだったので、英語クラスに入った。そこに6名のクラスメートがいたが、そのうちの一人が宮城毅くんというアメリカに農業研修にも行ったことのある沖縄の青年だった。物静かで、はにかんだ感じで言葉少なだったが、笑顔の素敵な人だった。ある時英語の先生が、これ沖縄の音楽なんだけど、とカセットテープの音楽を流すと、宮城くんはそのまま踊り始めた。いわゆるカチャーシーだが、内地の感覚でいうと、すぐに踊り出しそうな人じゃなかったので、びっくりしたけど、すぐ踊れるのである。これは10年住んだブラジルの人も同じで、音楽がかかるとすぐ踊れた。というかとにかく、自らの馴染んだ音がかかると、体が動く。踊りの本質はそういうもので、そういう中で、踊りが好きで、さらに踊ることに天賦の才能がある人が各地の踊りの形を作り上げ、舞踊として展開していったのだろう。
だから、音あっての踊り、唄あっての踊り、である。赤馬節は、八重山の座開きの踊りである。八重山にいた名馬赤馬が首里王に召され、首里に行ったが、言うことを聞かない。飼い主であった大城氏番が首里に登ると、赤馬は彼の言うことならなんでも聞く。その人と馬の心の通いあう様子に感動した首里王が、赤馬が大城氏番とともに八重山に戻ることをゆるした。赤馬が帰ってきた喜びを歌うのが、赤馬節であり、沖縄本島では「かぎやで風」が踊られるようなめでたい席では必ず踊られる。ただ、結婚式では、「出戻り」感があるため、避けられているようだが。踊りを習う人はまず、この赤馬節か、八重山のもう一つのめでたい踊りで、とりわけ新年に相応しい鷲ぬ鳥節のどちらかを習うことが多い。
もう40年近く前になるが、琉球大学八重山芸能研究会に所属して赤馬節を習った。大学生の部活だから、それこそ来る日も来る日も特訓。何度も曲を聴く。赤馬節のみならず、この時、先輩たちが唄ったり踊ったりした曲は、あまりに何度も繰り返し聞いたため、それこそ血肉となっている感じがある。赤馬節、安里屋節(あさどやぶし)、夏花(なつぱな)、高那節、祖納岳節(そないだきぶし)、まへーらつ、黒島口説(くるしまくどぅち)、久高節(くだがぶし)、弥勒節、桃里(とざとぅ)、真謝井(まじゃんがー)、川原山(かーらやま)……などなど今もはっきりと覚えている。だから、今回も赤馬節の方は、手は女踊りで違っても、音が完全に自分のものになっているので、そういう踊りはなんとか踊れるのである。
小浜節は好きだが、赤馬節ほどには体の一部になっていない。まずはこの音を体にしみこませること、と思い、それこそ朝に晩に小浜節を聴き続けた。一日30回くらい踊って覚えていこうとして、師範のビデオを見ながら練習する。このビデオを見て練習、というのも、おそらく踊りを習う本質からは外れていっているのだろうと思う。大体、ビデオがなかったのは、ついこの間の話なので、誰もが映像をスマホで見られるようになって、そんなに長い時間はたっていない。それまで踊りはどう習っていたのだったか。私自身も約40年前、赤馬節を習っていた頃、確かにビデオは存在していたが、それは誰もが気軽に手元で見られるものではなかった。やはり先輩に習いながらその場で覚えていったのに違いない。だからあまりスマホの映像に頼りたくないのだが、そうは言っても、今はそこにスマホのビデオが存在するので、つい頼ってしまう。このようにして何かが失われていく、とは思いながらも、安直な方法に流れていくのである。
ともあれ小浜節を聴き続け、とにかく踊りの手を覚える。覚えてからのブラッシュアップの時間をどれほど取れるか、が勝負だと思っていた。
結果として3週間弱の練習。1人で踊るのではなく3人で踊るから、息があっていなければならない。三線との音合わせも、リハーサルも全然合わなくて、もう、叱られてばかり。他の大きな演目は、一人か、ふたりで掛け合いの踊り、しかも、小浜節の3人よりベテランが踊るのでとにかく、公演の出来は、この小浜節の出来にかかっている、と言われた。公演の当日、たくさんの踊りの先輩方が、着付けやメイクのために馳せ参じてくださり、その方々の一つ一つのアドバイスが実に見事で、彼女たちのおかげで当日はなんとか揃って踊り上げることができた。
憧れ、は、かなうものなのだな、としみじみとうれしい思いでいる。八重山と何の関係もなかったはずの私が、たまたま大学院生の時に在籍した八重山芸能研究会で八重山の唄と踊りと芸能にふれ、それこそ一発ノックアウトというか、初球でホームラン打たれたというか、そんな感じの衝撃を受け、自らの土着の音とリズムを初めて聞いたような気がした。縁のない八重山の音を土着、というのも変なのだが、これはもう、おそらく、魂の世界の話なのだろう。心をわしづかみにされ、私は八重山民謡の音源と舞扇を地球の裏に10年住んでいた頃にも、携えていたのである。先輩方が踊る、西表島祖納の踊りである、祖納岳節にどれほど憧れたことだろう。スディナ・カカンの片袖を抜いて、紫のサジを頭に巻いて四つ竹でゆっくり踊る。地元祖納ではすでに四つ竹の祖納岳節は踊られていないというが、八重芸で取材し、踊られたこの曲は忘れられない。この時から、スディナ・カカンにサジ、という八重山の正装で踊ることは、私の憧れになった。
私は66歳である。踊りに入門するにも初舞台を踏むにも、年齢がいきすぎている。いきすぎていることなどわかっているのだが、石垣市民会館中ホール第530回“郷土芸能の夕べ”に出てしまって、もう後戻りできない、70まで踊らせてもらおう……と思っているのである。
 三砂ちづる (みさご・ちづる)
三砂ちづる (みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮育ち。津田塾大学名誉教授、作家。京都薬科大学卒業、ロンドン大学Ph.D.(疫学)。著書に『オニババ化する女たち』『ケアリング・ストーリー』『六〇代は、きものに誘われて』『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』『少女のための性の話』『少女のための海外の話』、訳書にフレイレ『被抑圧者の教育学』、共著に『家で生まれて家で死ぬ』他多数。