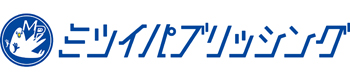- Home
- [Webマガジン]グローバルサウスの片隅で
- 「第21回 ブー(後編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる
最新記事
6.202025
「第21回 ブー(後編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる

(前編はこちら)
そんなわけで、苧麻を刈ってから苧引きまでを、初めて一人でやってみた。今まで何度かやっているが、教えてもらいながらやっていたのである。長袖長ズボンに軍手。苧麻をさわるとアクが手につくので、ニトリル手袋もつけた。このニトリル手袋は、100枚いくら、で売っている使い捨ての手袋であり、2020年の新型コロナパンデミック時に広く使われるようになった。スーパーのレジ打ちをなさっている方がいつも使っていたのでみな、みたことがあるのではないだろうか。流行当初、新型コロナウィルスは飛沫感染であると言われていたので手洗いうがいが必須、と言われ、手袋使用が重要、ということになったのである。私も家庭でニトリル手袋を購入し、外出して公共交通機関に乗らなければならないときなどはずっと手袋をして過ごしていた。その後、新型コロナウィルスはほぼ空気感染である、ということが発表されるようになり、空気感染であるならば、うがい手洗いは無駄とは言わないが、それでは全く追いつかないのであって、空気が動かない狭いところ、つまりは三密などを避けなさい、と言われるようになったのであるが、手袋使用はずっと続いていた。で、このニトリル手袋、慣れると、家事をするのに大変便利である。掃除、台所の皿洗い、ほか、特に冬場は冷たくないし、手が荒れないし、なかなかよろしい。新型コロナパンデミックが落ち着いても、このニトリル手袋を常備する習慣は続いて、今も、掃除用具入れにニトリル手袋を置いている。
苧麻の刈り取りもやってみると、うーん、これはもうちょっと成長させた方が良いのか、まだ細いのではないか、いや、もう、下の方が茶色くなっているから刈った方が良いか、といろいろ迷うし、葉を落として、外皮だけにするプロセスも、どうも一緒にやってもらっていた時ほどすっきりはできない。要するに慣れていない。
この皮を水につける。ここで私は大きく間違ってしまったことに後で気づく。アクをとる意味もあるのだろうし、繊維を柔らかくするのだろうから、水には長くつけた方が良いと思い、一時間以上つけてしまった。その方がいいだろうと思ったくらいで。ところが水に長くつけられた苧麻の皮自体が柔らかくなりすぎていて、苧引きするときに皮が取りにくいのである。以前教えてもらったときは、へらを当てるとぱきっという感じで、苧麻の皮が割れてそのまますーっと繊維をひきながら皮が取れていった。そのようでなければならない。水につけすぎた苧麻の苧引きは本当にやりにくくて、時間がかかってしまい、さらにあまりきれいに繊維が取れず、緑色が残ってしまった。苧麻の繊維は真っ白な方がいいのである。最初少し緑が残っていてもだんだん白くなる、と書いてある向きもあるのだが、島の方が引いた苧麻の繊維は最初から白い。これはだから私のやり方が良くないか、水につけすぎたかどちらかではないか、と思っているのである。後で教えてくださった方に報告すると、「あ、ごめん、水には5分以上つけちゃダメ、っていうのを忘れた」ということだった。はい、苧引きの前に皮を水につけるのは5分以下にしなければならないのだ。
私に苧引きを教えてくださった方の奥様が苧績みをされている。いまや人間国宝となられた八重山上布の織り手、新垣幸子さんに八重山上布の作り方を習われた方で、家計の足しに、と八重山上布を織っておられたが、手間の割には安定収入につなげることにも困難があるので、普通の仕事に転職され定年まで勤め上げられた。仕事を定年されてから、苧績みはまたやるようになって続けておられるという。今は織り手はいても、糸が足りないそうなので、糸を作っておられるが、時給にすると五十円にもならないような作業なので、お金を目的にやるのは割に合わない。定年後でお金のために働く必要はなく、手を動かしていることが好きだし、必要とされているので、やっておられるようだ。
まず、いろいろなものを準備する。糸がよく見えるように黒い布を作業する机と膝の上に置く。糸を湿らせながら行うので、トレイにスポンジを置いたものを用意しておく。指サックをはめて乾いたブーを割いて、糸のけばをとり、細い糸にしごいていく。教えてくださったミチコさんは、この段階で大変細い糸にするのが好き、とおっしゃる。本当に細い糸にされるので、織り手が好まれるのもわかると思う。糸の長さ自体は苧麻の長さしかないので、そんなに長くない。長くて30cm前後というところである。机の上に置いた黒い布の上にその糸を並べていく。
黒い布の上にかなり糸が溜まったら、それらの糸をつないでいく。短い繊維を一本の糸にしていき、その作業自体を苧績み、というのである。ここにかなり高い技術が求められる。下手なことをする糸が切れてしまうわけだし、継ぎ目が美しくないと、それは直接織物の質に関わるのは素人でもわかる。繊維の端を右に置いて、もう一つの繊維をとって先の部分を数センチ重ね、右手でコヨリを作るようにして二つの繊維をよる。乾いているとうまくできないのでスポンジで湿らせながら、やる。よった部分を右の繊維に寄せて左手でまたよる。引っ張ってみて一本の糸になっていたら完成・・・で、ミチコさんはもちろんどんどんつなげていかれるが私は全然できなくて、よっても、糸が外れてしまう。
ミチコさんは石垣に住んでおられて、竹富島には、何か行事がある年に数回くらいしかおいでにならないから、「じゃあ種子取祭の時にいくから、その時にやりましょう!」と、糸を入れる小さなカゴから、黒い布、指サック、スポンジ、など必要なものを過不足なく私のために集めてくださって全部袋に入れて持ってきてくださった。で、以上のことを教えてもらったのだが、一年目の種子取祭で、着付けの担当をしていたのと、客人が6名くらいきていたり、送迎をしたり、の裏のあれこれで、気持ちがウロウロとしており、これだけしっかり準備してくださったというのに、ミチコさんの指導にぜんぜんついていけず、あー、できません、また、やります、で終わってしまった。劣等生。全て持ってきていただいたお礼を申し上げて、復習して、また教えを乞うことになった。
ブーの糸をとる。まだ、できていないのだが、工程の全てを自分でやってみて、これは本当に大変なことだと思った。芭蕉布を作る糸芭蕉は、苧麻より倒すのが大変だったり、煮たりする工程も入り、もちろん細かいところは違うのだが、工程は似ている。はっきり言って、どちらも糸にするまで、本当に大変なのだ。八重山にもともとある苧麻や糸芭蕉で二世代前まで、島の女性たちは黙々と糸をとり、涼しい織物を作ってきたのだ。あまりに高価で手を出そうと思ったことすらないが、八重山上布や芭蕉布の着物をお持ちの方もおありだろう。高価な着物、意味では一桁違い、何百万、ということになってしまうような高級夏着物だが、それはそうだろう、手がかかりすぎる。糸にするだけで本当に手間がかかるのである。
これを経験していると、絹や綿というものの素晴らしさが改めて際立ってわかるようになってくる。木綿の糸造りも経験したことがあるが、木綿は、あの綿の実がふわり、ぽっ、と咲くと、もう、そのふわりとしたかたまりから直接糸をとることができる。綿くり器にかけると、タネが取れる。タネが取れた綿の実の繊維を広げ、そこから糸を出しながら糸車にかけて、よりをかける。次の綿の実の先に糸を置くとそこからどんどん糸が出てくる。おもしろいように一本の糸になっていく。苧績みのような作業なしに一本の糸がどんどん取れていのである。これ本当にすごいな、と思った。その綿糸を作って作り上げた布は、苧麻や芭蕉の布のように涼しくはないが、肌触りがふわり、と柔らかく、あたたかい。綿を知った人類の喜びと、広がりの速さが想像できる。
絹は、さらに、お蚕さんが糸をどんどん吐いてくださるわけである。また言うけど、短い糸をつなぐ苧績みのような作業とは違う。育ってきたお蚕様が自分で糸を吐き、繭を作っていく。なんと言うことであろうか。その美しさ、蚕という生き物の持つ、魔法のような力。そして、その繭から取り出される糸の信じられないような輝き。布に織り上げても光沢もあり、肌触りも優しく、なんと言っても、ただ、美しい。植物から糸をとるのとは違う、生き物から吐かれた糸の力、を感じることができる。
麻と木綿と絹と。八重山の中でもこれらの繊維が混じりあって使われるようになる。木綿については、八重山地方に17世紀くらいにもたらされたと言われており、石垣島では作られていたようで、民謡にも木綿の花のことが出てくる。竹富島でも木綿の栽培が試みられたことがあったようだが、台風の季節と重なることもあり、定着せず、竹富島で織られていた木綿のミンサー帯の糸は、島外から持ち込まれていたようである。養蚕に関しては、一世代前には桑を育ててかなり大々的に行われていたようで、島にはまだ、蚕の飼育場だった建物が残っている。グンボーと呼ばれる混紡の着物もかなり作られていたようだ。絹と麻、など異なる糸で織り上げられるきものが実用として使われたようだ。売るための着尺であれば、それは人頭税時代の織物と変わらない。混紡で作られた八重山交布が日々の衣の生活に残っていってほしい、と願っている今である。
 三砂ちづる (みさご・ちづる)
三砂ちづる (みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮育ち。津田塾大学名誉教授、作家。京都薬科大学卒業、ロンドン大学Ph.D.(疫学)。著書に『オニババ化する女たち』『ケアリング・ストーリー』『六〇代は、きものに誘われて』『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』『少女のための性の話』『少女のための海外の話』、訳書にフレイレ『被抑圧者の教育学』、共著に『家で生まれて家で死ぬ』他多数。