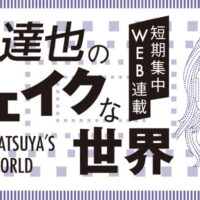- Home
- [Webマガジン]森達也のフェイクな世界
- 森達也のフェイクな世界「第1回 北京国際映画祭で笑いをとる」
最新記事
5.222024
森達也のフェイクな世界「第1回 北京国際映画祭で笑いをとる」

四月一七日午前七時。眠い目をこすりながら羽田空港第三ターミナルに着いた。八時五〇分羽田発JAL021便に乗らなければならない。今年で一四回目となる北京国際映画祭に『福田村事件』が招待されたのだ。
カウンターでチェックイン。渡されたチケットの左上には「business」と記されている。二度見したかも。ビジネスだ。
送られてきたEチケットをあらためて読み返す。確かにちゃんとビジネスシートと書いてある。気づかなかった。というか、ちゃんと読んでいなかった。
マニュアルを読むことが苦手だ。いや苦手のレベルじゃない。ほぼ読まない。世の中はマニュアルを読む人と読まない人で大別される。僕は後者だ。年末の商店街のくじ引きで当たったタニタの体重計すら、マニュアルを読めないのでいまだに使えない。最初の設定ができないのだ。
とにかく生涯で二度目か三度目のビジネス。一度目はいつだろう。二〇年ほど前に勤めていた大学の仕事でウランバートルに行ったとき、(姉妹校を締結する予定だったモンゴルの学校の教員が同乗していたからだと思うが)渡されたチケットはビジネスだった。二度目はその数年後、講談社が企画した姜尚中東大教授(当時)との対談の仕事でポーランドやドイツに行ったとき、ウィーンの空港から成田に戻る予定だったが、担当の女性編集者が姜とカメラマンと僕のチケットを持ったままチェックインに遅れてしまい、やむなく翌日のビジネスをとったのだ。
つまり一回目も二回目も、ひとりならばビジネスには乗れなかったはずだ。いわば漁夫の利。あるいは虎の威を借りる狐。でも今回は他力に頼ったこれまでとは違う。
……と胸を張りたいけれど、よく考えたら今回のビジネスも自分の器量ではない。北京国際映画祭は国家行事でもあるから、中国政府の恩恵を受けたとの見方のほうが妥当だ。
これまで五〇カ国以上は訪れているけれど、その内訳はすべて仕事と映画祭とピースボートだ。つまり自分の身銭で旅費をまかなったことは一度もない。すべてチケットは与えられてきた(だからいまだに航空券の買いかたがよくわからない)。もしも次の人生があるのなら、年に一回くらいは(身銭をはたいて)海外でバカンスをとれるような人生を送りたいと切に思う。
チェックインを済ませて保安検査場に行けば長蛇の列。でも案内板をよく見れば、ビジネスとファースト用の通路がある。そこは誰も並んでいない。この通路に進んでいいのだろうか。チェックの際に、おまえは違うとか身の程を知れとか言われないだろうか。
びくびくしながら係員にチケットを示せば簡単に通れた。気のせいか保安検査場の係官たちの態度も何となく丁寧だ。そういえばチェックインのときに「搭乗までラウンジで休んでください」と言われたことを思い出した。朝四時起きだから空腹だ。通路脇の売店でサンドイッチを買ってゆこうかどうしようと悩みながらサクララウンジに着いて扉を開ければ、広い室内にはビュッフェ形式の朝食が用意されている。しかもなかなか豪華。何よりも無料だ。その隣にはアルコールのコーナーもあって、ワインやビールが飲み放題。
ビジネスですらこの待遇なのだから、ファーストについてはまったく想像もつかない。アラブの大富豪のような時間を過ごせるのだろうか。深々とした椅子に座って考える。エコノミーとビジネスとファースト。飛行機のシートの選別は、普段はそれほど気にしないですむ経済的な格差を、これ以上ないほど露骨に可視化するシステムだ。言ってみれば大日本帝国時代の二等国民や三等国民。アジアやアフリカを支配していた欧米の植民地主義。バスのシートまで区分けしていたアメリカの黒人差別。なぜこんな前近代的なシステムはやめようと誰も言いださないのだろう。新幹線のグリーンですらそわそわと腰が落ち着かないというのに、日常的にビジネスやファーストを利用できる人たちは、どんな意識になるのだろう。自分は特権階級だと思い込んでしまう人もいるかもしれない。政治家はその典型だ。
一緒に行くはずの小林三四郎プロデューサーの姿が見えない。遅刻したのだろうか。でも搭乗直前に、ぎりぎり間に合ったとスマホにメッセージが届いた。映画祭が用意した彼のチケットはエコノミーだという。職業差別だと怒っている。
搭乗すれば椅子はゆったり。足を伸ばせるどころか、リクライニングを使えば完全に横になれる。北京まではほぼ三時間のフライト。短すぎる。これなら一〇時間でもかまわない。
ワインを飲みながら『ゴーストバスターズ/アフターライフ』を観る。モニターもエコノミーよりはずっと大きい。映画は凡作だったけれど、ダン・エイクロイドとビル・マーレイ、ハロルド・ライミスのオリジナルメンバーの顔は懐かしかった(ただしハロルド・ライミスだけは十年前に逝去しているので、CGで再現されている)。
北京に着く一時間前に、見逃していた『バービー』を見つける。三〇分だけ観て(バービーがバービーの国から現実にトリップするまで)、もっと早く観始めればよかったと後悔する。北京まであと二〇分しかない。まあ帰りもJALでビジネスだから、おそらく残りを観れるはずだ。
空港で小林プロデューサー、映画祭スタッフの高さんと合流。迎えの車に乗って宿泊先のホテル「ワンダ・ビスタ」に向かう。ホテルでは日中映画祭実行委員会の耿忠(コウ・チュウ)理事長が迎えてくれた。
部屋でしばらく休憩してから、六時に指定されたレストランに行けば、坊主頭で大柄な男が手を挙げながら立ち上がった。李纓(リ・イン)だ。日中映画祭実行委員会のメインスタッフである彼は、二〇〇七年に公開されたとき上映中止運動が起きて大きな話題になった映画『靖国 YASUKUNI』の監督でもある。会うのはそれ以来だ。
青島ビールを飲みながら広州料理を食べる。日本映画や中国映画の現状について話し合う。
食事を終えて三人はタクシーで次の店に向かう。紫禁城のすぐ後ろの湖の周囲の繁華街は、平日の夜だというのに人出がすごい。ここで合流したのは中国の映画研究者。男たち四人はバーでウィスキーを飲む。一一時に店は消灯。そこから再びタクシーで戻る。
ホテルの部屋でWi-Fiを繋ぐ。Googleはまったく繋がらない。LINE、Facebook、XなどSNSもまったくダメ。YouTubeも繋がらない。Outlookでかろうじてメールのチェックはできる。Yahoo!の画面は出るしYahoo!ニュースも見出しをクリックして記事を最後まで読むことはできるけれど、なぜか検索はできない。スマホでWhatsAppは時おり繋がるけれど、繋がらないときもある。しかも小林プロデューサーの部屋では、このネット環境が微妙に違うようだ。さらにスマホとPCもやっぱり違う。つまり規則性がわからない。
検閲は基本的にはAIがやっているが、中国政府は通信を監視するために五万人以上のスタッフを配置していて時おり人為的な判断をしています、と中国のスタッフに聞いた。実際のところはわからない。これまで『Blue Island 憂鬱之島』や『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』など多くの反体制香港映画の配給や製作に関わってきた小林プロデューサーは、「自分はいつ拘束されてもおかしくないよな」などと半ばは冗談(ということは半分は本気)でつぶやいている。
翌一八日は北京映画祭初日。レッドカーペットを歩かねばならない。ホテル玄関で待っていた送迎車に乗って、北京郊外にある北京延吉湖国際会議展覧センターに向かう。到着して驚く。何の冗談だと言いたくなるほどに巨大な建造物だ。そしてものものしい警備。防弾チョッキを着用した警官だけでも数百人はいる。セキュリティチェックも厳しい。俳優も監督もプロデューサーも、みなX線検査を通過しないと中には入れない。
レッドカーペットの周囲には数百人の観客たち。こんな不便な場所までよく来るなあと思っていたら、中国スタッフが「あの人たちのほとんどは一般人ではないはずです」と僕に言う。
「そうなの?」
「政府関係者の招待です」
これも実際のところはわからない。とにかくグレイゾーンが多すぎる。もちろんグレイゾーンは大切だ。でも法やシステムの場合は、できるかぎりクリアにするほうがいいはずだ。そこで気づく。この国の多くの人は(もちろんすべてではない)、ある一線で思考や煩悶を止めている。なぜなら主語は常に国家か政府。自分たちが主権者であるという意識が薄い。
それがあきらめなのか、あるいは自由な表現や報道が規制された環境に馴化されているからなのか、あるいは(多くの中国の知識層が言うように)過渡期ゆえの一段階だと思っているのか、僕にはわからない。おそらくはひとつではないだろう。とにかくレッドカーペットを歩く。写真を撮られる。セレモニーはここで終わり。ホテルに戻りましょうとスタッフに言われる。でもまだレッドカーペットは続いている。
まだ一時間は続きますよ、それから来賓紹介です、市長とか行政局の偉い人たちとかの長い挨拶を聞きたいですか。
帰っていいの?
みんなレッドカーペットを歩いたら帰ります。
もしもここが日本なら、ほとんどの人は律義に最後までいるだろうな。たぶんここは日本人と中国人の大きな違いだ。集団化しやすいことは共通しているけれど、身も心も集団の一部になる日本人とは違い、中国人は一人ひとりの個が強い。
ホテルに戻って軽い夕食を済ませてから、ホテル横のワンダシアターに向かう。『福田村事件』一回目の上映だ。
六〇〇ほどの客席はフルハウス。入りきらずに帰した客もおおぜいいたという。終わる直前にひとつだけ空いていた椅子に座ってすぐに驚いた。後ろから蹴られたのだ。反日の人だろうか。ふさけるなよ日本鬼子(リーベンクイズ)、こんな映画を作りやがって。上映が終わったら殴られるのだろうか。でもこの映画だってどちらかと言えば反日なのに。……あれ。どうも様子がおかしい。蹴るのではなく撫でられている。そこで気づく。椅子の背にマッサージ機器が埋め込まれているのだ。
上映が終わってから、小林とステージに上がる。司会からマイクを渡されて最初に、マッサージに驚きました、と言えば場内は大爆笑。これで良い。上映後のトークは好きではない(上映前は論外)。だって質問に答えたくない。だからこの日も僕はいくつかの質問に対して、想田和弘直伝の「あなたはどう思いましたか」と切り返した。
「映画は観た瞬間にその人のものになります。もちろん僕の意図はあります。でもそれは言いたくない。答え合わせなどしたくないし、そもそも正解もないと思っています。あなたの解釈でいいんです」
どちらかといえば素気ない態度だったと思うけれど、質疑応答を終えてステージから降りようとしたら、チケットやチラシを手に多くの人たちが集まってきてサインを求められた。これほど多くの人たちから歓迎されたことは、ちょっと記憶にない。
ホテルに戻ってから、耿忠さんともう一人の女性スタッフ、小林と四人で天安門近くの屋台街に行く。屋台と聞いていたけれど正確には屋台ではない。雰囲気としては西荻の飲み屋ストリートだ。そのうちの一軒でぬるい北京ビールを飲みながら、水餃子に揚げたピーナツにピータンなどを食べる。でも食べきれない。一皿のボリュームが圧倒的すぎるのだ。途中から李纓も合流して、ビールをパイチュウ(白酒)に替える。アルコール度数は四五度。楽しい夜だった。
翌四月一九日は、日本映画週間のオープニングセレモニーだ。今回選ばれた四作品は、『不死身ラヴァーズ』(監督・松井大悟)、『白鍵と黒鍵の間に』(監督・富永昌敬)、『愛にイナズマ』(監督・石井裕也)、そして『福田村事件』だ。北京英皇電影城のIMAXスクリーンの前でぎっしりと埋まった観客席に挨拶して、その後は日本大使館が後援する歓迎レセプションが行われた。金杉憲治特命全権大使など大使館職員たちに挨拶される。
その合間にメディアからの取材。一人の中国人記者に「好きな中国映画は?」と質問されて、僕は岩波ホールで観た『山の郵便配達』を挙げた。半分はそのときの気分。違うときに質問されていたら、チャン・イーモウの『初恋のきた道』と答えていたかもしれないし、フー・ボーの『象は静かに眠っている』を挙げていたかもしれない。本当はチャウ・シンチーの『少林サッカー』がいちばん好きなのだけど、あれは香港映画だ。
それから三〇分後、一人の男性が目の前に現れた。
「『山の郵便配達』の監督の霍建起(フォ・ジェンチイ)さんです」
そう紹介されて唖然。ドッキリカメラかと思った。出来過ぎだけど偶然だ。霍監督も式典に一緒に参加する予定だったのだ。「あなたの映画を絶対に観るよ」と霍監督は言ってくれた。
式典では、金杉大使に続いて中国映画業界や東京国際映画祭のトップたちの挨拶が続き、その後に壇上でスピーチを促された僕は、『福田村事件』の意義を質問されて、以下のように答えた。
「人は失敗して成長します。もしも失敗を記憶せずに、運動会で一番になったとか一流大学に入ったとか聡明で美人の奥さんと結婚できたとか成功体験ばかりを記憶している人がいたらと想像してください。薄っぺらで魅力のない人になっているはずです。国も同じです。失敗や加害の記憶から目を逸らすべきではない。でも今の日本はそうなっています。本来なら教育とメディアがこうした記憶を維持するための装置だけど、もしもメディアと教育が委縮しているならば、映画がその役目を担う。そんなことを思いながら、この映画を作りました。そして僕から見ると、今の中国も日本と同じです。負の記憶を忘れようとしている。成功体験ばかりを歴史に残そうとしている。ならば同じ過ちをまた繰り返します」
通訳の王さんが終盤で激しくむせてしゃべれなくなってしまい、まずいことを言ったのでしょうか、と思わず言えば場内は大爆笑。終わって多くの中国映画関係者たちから、「とても良いスピーチだった」と肩を叩かれた。ただし中国メディアが伝えるのは前半から中盤まで。王さんがむせた終盤のフレーズは絶対に伝えないと多くの人に言われた。
翌日、スケジュールをすべて消化して東京へと戻る。ビジネスのシートで『バービー』の残りを観たけれど、展開する男社会やマチズモへの反発が何となくベタベタで平面的でつまらない。実のところ終盤はリクライニングが快適すぎてほぼ寝ていたので、機会があればもう一回観てみよう。
森達也(もり・たつや)
1956年広島県生まれ。映画監督・作家。立教大学法学部入学後、様々な職種を経てテレビ番組制作会社に入社。98年オウム真理教のドキュメンタリー映画『A』『A2』で内外の高い評価を得る。監督作に『FAKE』、『i-新聞記者ドキュメント』、『福田村事件』。著書に『A3』(講談社ノンフィクション賞受賞)、『たったひとつの「真実」なんてない』『虐殺のスイッチ』ほか多数。YA向けの著書に『いのちの食べかた』『フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ』『ぼくらの時代の罪と罰』がある。