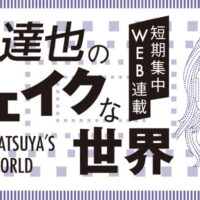- Home
- [Webマガジン]森達也のフェイクな世界
- 森達也のフェイクな世界「第2回 味方をしてくれというつもりはない」〜パレスチナ難民キャンプ
最新記事
6.52024
森達也のフェイクな世界「第2回 味方をしてくれというつもりはない」〜パレスチナ難民キャンプ

今日の日付は6月3日。イスラエル・パレスチナ問題について最新の(大きな)ニュースは、バイデン大統領がイスラエルとハマス双方に呼びかけた停戦への新提案だ。以下は6月1日 21時34分に配信されたNHKWEBのニュースだ。
(前略)アメリカのバイデン大統領は、31日、イスラエルがハマスに対し、戦闘休止などに向けて新たな提案を行ったと明らかにし、受け入れるよう求めました。
提案は3段階に分かれ、
▽第1段階では6週間、戦闘を休止し、イスラエル軍がガザ地区の人口密集地から撤退するとともに、収監しているパレスチナ人を釈放する代わりにハマス側が女性や高齢者などの人質を解放するとしています。
▽第2段階では恒久的な停戦や残りの人質全員の解放を進めること、
▽第3段階では復興計画の開始などが含まれているということです。イスラエルの首相府はバイデン大統領の演説のあとに声明を出し「ネタニヤフ首相は交渉団に人質解放という目標を達成するための提案を示す権限を与える一方で、人質の解放とハマスの壊滅という目標が達成されなければ戦争は終わらないとしている。条件をつけて段階的に移行するというイスラエル側の提案はこうした原則を維持することを可能にする」などとしています。
イスラム組織ハマスは31日、アメリカのバイデン大統領が演説で言及した提案について「肯定的に受け止めている」とする声明を発表しました。
声明では「イスラエルが提案を実行すると明言するならば、恒久的な停戦やイスラエル軍のガザ地区からの完全な撤退、避難民の帰還などに基づくいずれの提案にも、積極的かつ建設的に応じる用意がある」としています。(後略)
バイデンのこの提案に対して国連のグテーレス事務総長は、「これが恒久的な平和に向けた当事者間の合意につながることを強く望む」とするコメントを出し、EUのボレル上級代表はSNSで「戦争を今すぐに終わらせなくてはならない」として、提案を全面的に支持する考えを示している。
何だろうな。既視感だらけ。ハマスが奇襲攻撃をしかけた昨年10月7日以降、ずっと同じことをくりかえしている。予想だけど、ハマスが仮にこの条件を飲んだとしても、ネタニヤフ首相が連立する右派政党の意向を配慮して前言を翻す可能性は高い。ならばやっぱり同じことの繰り返しだ。既視感ともうひとつは違和感。特に報道で使われる言葉に対して。
少なくともガザ地区をめぐる今の状況については、「戦争」という言葉は当てはまらない。戦車に投石する少年たちが体現するインティファーダも含めて、この構図はあまりに不均等だ。戦争とは言えない。とはいえ、アメリカ従属が大前提である日本のパブリックメディアとしては、「虐殺」はさすがに使えない。そんな葛藤が「戦闘」という言葉に表れているのだろうか。それと「恒久的な停戦」という言葉の意味がわからない。本音としてはパレスチナの民を「約束の地」から一人残らず駆逐したいネタニヤフがこのフレーズを使ったのかもしれないが、いずれにせよ恒久的に停戦するならば、それは「終戦」と訳すべきではないのか。
既視感と違和感だらけではあるけれど、これまでの経緯と違いがあるとしたら、イスラエルに対する国際社会総体としての温度だろう。2024年5月28日以前には193の国連加盟国のうち146の国がパレスチナを国家として承認していたが、5月28日にはノルウェーとスペイン、アイルランドの3か国が、その二日後にはスロベニアも新たな承認を表明した。パレスチナに対する姿勢の変化というよりも、国家承認に激しく反発するイスラエルに対する変化だと思う。
ここまでを書いて考えた。イスラエル・パレスチナ問題について、僕はいつ知ったのだろう。いつから意識し始めたのだろう。
パレスチナ解放人民戦線(PFLP)が計画して日本赤軍3名が実行部隊となったテルアビブ空港乱射事件が発生したのは1972年。この時期の僕は中学三年生。事件は世界的なニュースだったから記憶にはあるけれど、日本の過激派が海外でテロ(この時代にテロという言葉は一般的ではなかったはずだけど)を起こしたくらいの認識だったと思う。この時点では背景や理由についての知識はほぼ白紙だったはずだ。
少なくとも高校の世界史で習った記憶はない。ただし中東戦争について教科書が触れないはずはないから、シオニズムという言葉を教えられたかどうかはともかく(たぶん教えられていない)、イスラエル建国くらいは習ったはずだけど、もちろん深くは考えていない。
テレビの仕事をしていた20代後半から30代にかけて、パレスチナ問題について深く考えた記憶もない。
いやそもそもこの時期の僕は、政治や社会については全方位的に、深く考えることはしなかった。選挙すらまともに行っていない。
やはりスタートは『A』撮影と発表の時期である30代後半から40代にかけてだ。1996年からほぼ一年と半年、僕は一人で(後半はプロデューサーの安岡卓治が同行することも何度かあったけれど)オウム施設に通い続けた。言い換えれば異界と俗世を往復し続けた。ただし異界にいたのは異人ではない。僕たちと何も変わらない人たちだ。でもオウム施設から振り返れば、今まで自分が帰属していた社会が異界となり、メディアや警察や一般社会に帰属する人たちのこれまで見えなかった部分が見えてきた。この撮影を通して、メディアやドキュメンタリーに対する認識が大きく変わっただけではなく、自分自身も変化した。
『A』がプレミアム上映された1998年の山形国際ドキュメンタリー映画祭で、コンペティション作品のひとつだった『ハッピー・バースデー、Mr.モグラビ』を観た。監督はイスラエル人のアヴィ・モグラビだ。
『ハッピー・バースデー、Mr.モグラビ』の概要をざっくりと説明すれば、メインの被写体は監督であるモグラビ自身だ。つまりセルフ・ドキュメンタリーとの見方もできる。母国の建国50周年記念の映画製作を依頼されたモグラビは、ほぼ同じタイミングで誕生日を迎え、さらにパレスチナ政府からも自分たちの被害の記憶(ナクバ)をテーマにした記録映画の監督を依頼される。自分はどちらの立場なのか。悩むモグラビは、ちょうどこの時期に引っ越しする予定だった。ところが新居の完成が遅れて引っ越しができず、今住んでいる家の買主から契約不履行で訴えられるというトラブルが発生する。
自身をめぐるこれらの混乱と騒動をカメラが記録する。でも観客は途中で気づく。どうやらこれはフェイクだ。そもそもユダヤ人であるモグラビにパレスチナが国家的な仕事を依頼するはずがない。ただしどこまでがフェイクなのかわからない。引越しのエピソードは本当かもしれないし、建国50周年の映画制作も本当かもしれない。あるいはすべてがフィクションである可能性だってもちろんある。
こうした作品も(本人が自称すれば)海外ではドキュメンタリーとしてカテゴライズされることにまずは驚いた。同時にイスラエル・パレスチナ問題の複雑さと現状を知った。
ちなみにこのとき、『A』を観終えたモグラビが「監督に聞きたいことがある」と言っていると映画祭スタッフから伝えられ、山形市内のカフェで一時間ほど話をした。僕と彼はまったく同年齢だ。でもモグラビはとにかく顔が髭面で怖い。しかも大男だ。何を質問されるのだろうと内心はびくびくしながら挨拶してすぐに、「作品についての責任をおまえはどう考えるのか」と訊かれ、少し考えてから「責任なんかとれるはずがない」と答えた。無言でしばらくうなずいてからモグラビは、「わかった。その答えを聞きたかった」と言いながら破顔一笑した。
この後にパレスチナ問題をずっと撮ってきた古居みずえや土井敏邦のドキュメンタリー映画を観て、同様にパレスチナ問題を継続的に取材している綿井健陽や豊田直己、広河隆一など戦場ジャーナリストたちの写真や文章に触れた。
アウシュビッツ強制収容所に足を運んだのもこの頃だ。展示されたユダヤ人の遺品や膨大な髪の毛(生地にする予定だったらしい)、チクロンBの空缶を見たりガス室や焼却炉に案内されたりしながら、凄まじい被虐の記憶に震撼した。でも同時に違和感も持った。一方的な被虐の記憶は加害側をモンスター化すると考えた。ならば当時のナチスドイツに帰属する人たちは、みな血に飢えた野獣のような存在だったのか。あるいはナチスを支持した一般国民の多くは、冷酷で残虐な人たちだったのか。もちろんそんなはずはない。このときはアウシュビッツだけではなくドイツ国内のザクセンハウゼンなど多くの強制収容所を訪ねたけれど、そのたびに違和感は大きくなった。
『A』に続き『A2』を発表して数年後、二万人近いパレスチナ避難民が暮らすヨルダンのスーフ難民キャンプのアルヘンリー家にホームステイした。この家に暮らす五人兄弟と夕方にはキャンプ内の市場に行き、露店で揚げたてのファラフェル(ソラマメとヒヨコマメのコロッケ)を買い食いしたりカフェでトランプに興じたりした。家に戻れば食事の用意ができていた。ようやく台所から出てきた母親と長男の妻に挨拶する。夕食のメニューは、鶏肉のケバブに、パセリやトマトをたっぷり使ったタボーレというサラダ。ナスをペースト状にしてスパイスを効かせたモウタベル。他にもたくさんの料理が並べられている。
食事後に風呂。しばらく待たされた。案内されたバスルームは、コンクリート打ちっぱなしの小さな個室だった。もちろんバスタブなどない。シャワーだけだ。お湯は出ない。まあそれは当たり前。でもアルヘンリー家のバスルームの床には、一〇個ほどのプラスティックのバケツやタライらしきものが並べられていて、中には熱いお湯がたっぷりと入っていた。日本人は入浴の際にお湯を欲しがると聞いていた兄弟たちが、鍋で沸かした湯をバスルームまで運んだのだ。
夜中に兄弟たちとパソコンでガザ地区の映像を見た。イスラエルの砲撃で破壊されるガザの街。イスラエル兵に銃撃される子どもたち。地面に転がる家族の焼死体。モザイクなしだ。無言で見ていたら、「日本人はパレスチナ問題に関心を持っているのか」と三男に質問された。
「……正直に言えば、関心を持つ人はあまり多くないと思う」と僕は言った。
「おまえ自身はどう思っている?」
「複雑だよ。簡単には言えない」
「味方をしてくれというつもりはない」と長男が言った。
「でもせめて現実を知ってほしい。ガザとヨルダン川西岸地区で何が起きているのか。おれたちはなぜ故郷に帰れないのか。残った同胞たちはどんな日々を送っているのか。せめて知って考えてほしい」
このときに自分が何と返事をしたのかは覚えていない。何も言えないまま、うなずいただけかもしれない。
おそらくこの時期に、ホロコーストでのサバイバーであると同時にイスラエルによるパレスチナ占領政策に反対を表明し続けた作家プリモ・レーヴィの『これが人間か』を読んだはずだ。パレスチナ問題をコンセプトにしたアルバム『オリーブの樹の下で』をPANTAがリリースしたのは2007年。もちろん全曲聴いた。そしてやはり同時期に、連合赤軍事件をテーマにしたシンポジウムにパネラーとして参加して多くの赤軍派関係者と知り合いになり、平壌に行ってよど号メンバーたちの家で寝食を共にした。レバノンの映画祭に行ったときは、テルアビブ空港乱射事件の実行犯の一人でアラブにとっての英雄である岡本公三に会えるかもしれないとの情報が届いて、このときはさすがに緊張した(結局は会えなかった)。
そして今は思う。多くのユダヤの民が差別され迫害されて苦しみながら死んでいったことは確かだ。しかもそんな時代が2000年以上も続いた。その歴史を知ることは大切だ。でも1948年のイスラエル建国以降、パレスチナの民を差別して迫害してきたのは、シオニズム思想に染まったユダヤの側だ。それは現在のネタニヤフ政権でピークに達しているけれど、建国以来ずっと常軌を逸してきたのはユダヤの側だ。
今回は最後に、村上春樹がエルサレム賞を受賞したときのスピーチの一部を引用する。他の作家の言葉を安易に引用すべきではないとは思うけれど、このスピーチを初めて読んだとき、僕はとても感動したし共感もした。ほぼ完ぺきだと思う。全文はこの数倍はある。できれば全部読んでほしい。
(前略)とても個人的なメッセージを伝えさせてください。私が小説を書く時にいつも、心にとめているものです。紙に書いて壁に貼るようなことはしていません。むしろ心の壁に刻まれているもので、次のようなメッセージです。
「高く強固な壁とそれに打ち砕かれる卵があるなら、私は常に卵の側に立つ」
壁がどれだけ正しく、卵がどれだけ間違っていたとしても、私は卵の側に立ちます。何が正しく間違っているかは他の誰かが決めるでしょう。おそらく時間や歴史が決めることでしょう。もしも、何らかの理由で壁の側に立つ小説家がいたとしたら、その作品にどんな価値があるといえるでしょうか?
このメタファーは何を意味するでしょうか?とても単純で明確な時もあります。高く強固な壁は爆撃機や戦車、ロケット、白リン弾です。卵はそれらに押しつぶされ、焼かれ、撃たれる、武器を持たない市民です。それがこのメタファーが持つ意味の1つです。
しかしもっと深い意味もあります。こう考えてみてください。私たちそれぞれが、多かれ少なかれ卵なのだと。私たちそれぞれが、壊れやすい殻に閉じ込められた、ユニークでかけがえのない魂なのだと。私もそうですし、みなさんもそうです。そして私たちそれぞれが、程度の差はあれ大きな壁に直面しています。
その壁には名前があります。「体制(システム)」です。体制は本来私たちを守るためのものですが、時に独り歩きして私たちを殺し始め、私たちに人を殺すよう仕向けます。冷酷に、効率よく、システマチックに。(後略)
(出典)
NHK NEWS WEB「イスラエルがハマスに戦闘休止へ新提案 米大統領が明らかに」https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240601/k10014467881000.html
HUFFPOST「村上春樹さん「常に卵の側に立つ」ガザ侵攻したイスラエルで伝えた、たった一つのメッセージ【改めて読みたい】」https://www.huffingtonpost.jp/entry/haruki-murakami-jerusalem-prize-speech_jp_65362f0ae4b0689b3fbd1c7e
森達也(もり・たつや)
1956年広島県生まれ。映画監督・作家。立教大学法学部入学後、様々な職種を経てテレビ番組制作会社に入社。98年オウム真理教のドキュメンタリー映画『A』『A2』で内外の高い評価を得る。監督作に『FAKE』、『i-新聞記者ドキュメント』、『福田村事件』。著書に『A3』(講談社ノンフィクション賞受賞)、『たったひとつの「真実」なんてない』『虐殺のスイッチ』ほか多数。YA向けの著書に『いのちの食べかた』『フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ』『ぼくらの時代の罪と罰』がある。