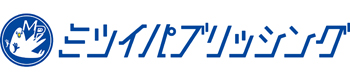- Home
- [Webマガジン]ダブリンつれづれ
- 「第21回 アラン島」ダブリンつれづれ / 津川エリコ
最新記事
12.132024
「第21回 アラン島」ダブリンつれづれ / 津川エリコ

アラン島へ出かけた。多分七年ぶりではないかと思う。東のダブリンからほぼ真西へアイルランドを横断する。島へのフェリー乗り場まで、休憩を入れなければ車で三時間半の行程。アイルランドは小さな国だ。フェリーで四十分。島に四十年住む友人宅に二泊させてもらった。二日目は大いに晴れ、大西洋側に面した島の崖際に沿って歩いた。波に深く抉られた崖の上部は、岩棚が一枚板のように海へ突き出している。崖際はつづら折りになっているので、振り返ってみて初めて、自分が空洞の上に突き出した岩棚の上を歩いたのだと気付かされる。白い波が崖に体当たりし砕ける時、私は海への畏怖と憧れを同時に感じる。崖縁に沿って、槍のように先の尖った縦長の石が人の手で垣根として巡らされている箇所もある。それは、歩く人のためではない。家畜の牛の安全のためだ。ところどころに草地があり、牛の糞も見かける。逆光でシルエットになった一頭の牛が、遠くの丘に長い間動かず、まるで島に君臨する王のように見えていた。
アランの地形は、対岸のバレンと呼ばれる石灰岩の丘陵と海底で地続きである。十七世紀、カトリック征伐にやって来たクロムウェル軍の司令官エドモンド・ルドローが、バレンを
「ここには人を溺れさせる水も無く
人を吊るす木もなく
人を埋める土もない」
と言い表した。たしかにバレンは、遠目には岩ばかりの不毛の地に見えるが、岩盤に走る割れ目に溜まった土に、地中海性植物と高山植物が同居する稀な地域である。暖流であるメキシコ湾流と石灰岩が吸収する太陽熱で、バレンは地中海性気候を作り出し、また高山植物に欠かせない光の絶対量を、石灰岩と海からの反射で満たしているというわけだ。私はスイスの標高二〇〇〇メールの山腹で見た青いリンドウの花を、バレンでも見たことがある。
本土に面したアランの東側には白砂の浜もあるが、大西洋に面した南西側は切り立った岸壁が続く。時には波際に出ることもあるが、昨日、砕かれたばかりのような鋭い角のある岩の上ばかりを歩くので、一歩一歩、足元に注意を払わなければならない。他のことを考える余裕がない。それがかえって頭を解放する。「黒い砦」と呼ばれる石の建造物に出るまで、三時間、誰にも会わず歩いた。広い空にカモメも飛んでいなかった。皮の登山靴は尖った石でキズだらけになり、私はそれを見て満足だった。
イニシモアは三つのアラン諸島の一番大きな島で、単にアランとも言われる。三つの島はイニシモア、イニシマーン、イニシーアであり、なかなか響きがいい。訳すと大きな島、真ん中の島、東の島となり、なあんだという気にもなるが、何でもない言葉がこんな風に快く響くのがアイルランド語だ。
九〇年代に私がツアーガイドをしていた頃、年によって一年に三度もアランに来ることがあった。島の産業は、漁業と観光である。島のミニバスに乗り込んで島内を巡る。運転手兼ガイドの島の青年が「島の産業は、冬は漁業で魚を釣り、夏は観光で観光客を釣るのです」と言ったものだった。観光客を釣るという言い方は、日本人には受けないと思い、私は訳さなかったのを覚えている。
ツアーは日帰りが多く、夕方六時の最終フェリーに乗り込みデッキから遠くなっていく灰色の島影を見る時、私はいつも大きな安堵に満たされた。その日の私の仕事が終わったという安堵ではない。島の気持ちになっての安堵だった。
観光客がいる限り、島は安心できない。観光とは、訪れる者から何らかの利益を得なければという因果な商売であり、島民の多くが何らかの形で観光に関わり、潤っている者とそうでない者の間に複雑な心理を生じさせている。きっと島は、去っていくフェリーをホッとした気持ちで見送っているだろうという安堵だった。島の家々の屋根の多くは灰色のスレート石が使われ、壁は白い。島の大部分を構成している石灰岩と静かに調和している。埠頭から離れて行くときに見える島が一番きれいだ、と私はいつも思ってきた。
アイルランドの劇作家J・M・シングは、一八九八から一九〇二年にかけて五度、アラン諸島を訪れている。最初の四回の紀行が『アラン島』として一九〇七年、シングの死の二年前に出版され、日本語にも早くから翻訳された。その頃、島に来る者と言えば文化人類学者が多く、島民の頭の大きさを測ったりしたそうだ。シングは、学者としてではなく、暖炉を囲んで話を聞く島の人に混じった。彼らの領分に入って彼らの流儀を尊んだ。手品をして見せたりヴァイオリンを弾いたりもした。彼の劇の多くが、島の年寄りたちからアイルランド語で聞いた話に着想を得ている。
「島人たちの知性と魅力の大部分は、ここには分業というものがないことと、それにともなって個人の能力が多方面に発達していることに由来するだろう。ひとびとの幅広い知識と技能は、精神の活発な働きを必要とするからである」
J・M・シング『アラン島』栩木伸明訳、みすず書房、2005年
砂と海藻から土を作る。畑、魚漁、家の建築、屋根葺き、パンプーティ(一枚皮から作る靴)、ゆりかご、棺桶、カラハと呼ばれるカヌー造りと修理。季節によって仕事の種類も変わる。そしてアイルランド語と英語の二か国語を話す。いろんなことができるために魅力的な人間になっている、というシングの観察に説得力がある。特定の分野のエキスパートになることを選ばなければならない現代人とは、随分違う生き方である。現代人は、分業が発達した世界で、生きていくために必要なことをするという実感がとても希薄になっている気がする。
シングが歩いていると、島の人が時間を訊いてくる。島には神父以外に時計を持っている人がいなかった。ミサを知らせる教会の鐘が唯一の時だったが、シングは時計になったようだ。
島には犯罪人が逃れてくることがあり、島の人は彼らを匿ってこっそりアメリカへ逃がしてやる、ということもあったらしい。それは、イギリスが作った刑法への反発もあるが、「(犯罪を起こしたのは)よっぽどのことがあったに違いねえ」という同情心かららしい、とシングは言う。犯罪人を責める代わりに、誰にだってそういうことは起こりうる、と考える。
これに着想を得て、シングは『西国の伊達男』を書いた。これは、シングの亡くなる二年前、一九〇七年に初演となった。初日に観衆が暴動を起こしたのは、あまりに有名な話である。このころ、アイルランド独立の気運が高まっていて、この劇は観衆の中にいた愛国主義者たちを怒らせた。暴動を起こした観衆は、この劇ではアイルランド人が揶揄されていると思い込んだ。劇の主人公、クリスティは父親を殺してある西の村へ逃げて来る。パブにいた村の男たちや、パブの持ち主の娘、ペギーンは驚きながらもクリスティを勇気ある男と見る。今まで、ずっと何も起こらない人生だった若いペギーンにとって、父親を殺した男に会うというのは何と劇的なことだったろう。同時に、父親を殺すということに神父、教会、英国といった権威への反抗を見ていると考えられないこともない。クリスティは村で英雄視された。一方、アートと言うのは民族の自覚と誇りを促すものでなければならないと主張する愛国主義者たちは、「アイルランド人はそんなモラルのない馬鹿なやつではない」と言って怒ったということだ。
シングは、この劇で話される英語にアイルランド語話法とアイルランド人独特の発音を持ち込んだと言われる。シングは植民地で暮らす民衆の英語が、アイルランド語と混成したユニークな発想と表現力を持つことに注目し、それを生き生きとした台詞に反映させた。初演では受け容れられなかった『西国の伊達男』であるが、その後は世界各地で上演されている。シングが生きていた頃からもう百年以上も経ち、アイルランドは独立国として大きく変化した。彼は、失われていくものをそうとは知らずに記録していたようだ。彼が出会った人々は、何度も帰って来て舞台で話し続けている。
参考文献:
『アイルランドの創出 現代国家の文学』デクラン・カイバード 坂内太訳 水声社 2018年
『アイルランド文学 その伝統と遺産』木村正俊編 開文社出版 2014年
『アラン島』J.M. シング 栩木伸明訳 みすず書房 2005年
Wild Plants of The Burren and Aran Island Charls Nelson Collins Press 1999
Edmund Ludlow: https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Ludlow
津川エリコ
北海道釧路市生まれ。ダブリン在住。『雨の合間』(デザインエッグ)で第55回小熊秀雄賞受賞。小説「オニ」(『北の文学2022』所収、北海道新聞社)で北海道新聞文学賞受賞。著書に詩集『アイルランドの風の花嫁』(金星堂)、随筆集『病む木』(デザインエッグ)があるほか、詩集アンソロジー”Landing Places”, “Writing Home”, “Local Wonders”(いずれもDedalus Press)に作品所収。