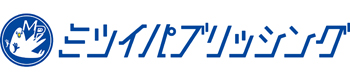- Home
- [Webマガジン]グローバルサウスの片隅で
- 「第19回 チテンゲ」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる
最新記事
5.162025
「第19回 チテンゲ」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる

アフリカ南部にある国ザンビアで暮らしたのは1984年のことである。約40年も前のことだ。その頃はまだ、人の肌の色で人間を差別しても良いというアパルトヘイト政策が南アフリカではとられていた。南アフリカの周囲のブラックアフリカ諸国は、アパルトヘイトと戦うフロント・ライン諸国と呼ばれていた。アパルトヘイトに反対し、ネルソン・マンデラを思想的な中心とする南アフリカの黒人たちのANC (African National Congress:アフリカ民族会議)は、当然南アフリカ国内では非合法であり、ザンビアの首都ルサカにその本拠地があった。つまり1984年当時、ザンビアはフロント・ライン諸国の最もフロントにいた。実際には、南アフリカとザンビアの間にはジンバブウェという国があったが、1980年に白人支配から脱したばかりの当時まだ新しい国だったから、やはりザンビアがフロント、という感じだったのだ。
当時日本はすでに経済大国としてその存在感を世界に示していて、もちろん黄色人種もカラード(colored)として法律で差別されている南アフリカにあって、双方に都合の良い商売相手であったことから日本人は「名誉白人」(honorary white)という、誠に不名誉極まりない称号を得て、南アフリカで経済活動を行っていた。私が通った薬科大学は小さな単科大学だったが、歴史学者・井上清の弟子であった大沢基という差別の歴史を研究する先生が専任教員として歴史を教えていて、この人がアフリカ行動委員会と呼ばれていた日本国内のアンチアパルトヘイト運動に関わっていたから、この「名誉白人」を不名誉なこととして反対運動を行ったり、クルーガーランドコイン(金貨である)とかダイヤモンドとかアップルタイザー(今はすっかりお馴染みになった、りんご100%の炭酸飲料水である)の不買運動にも馴染みはあったので、ANCがその本拠地を持つザンビアへの赴任は望むところだった。
薬学部のまだなかったザンビアで、薬関係の仕事を担うのは薬剤助手(pharmacy assistant)と呼ばれる職種で、首都ルサカのエブリン・ホーン・カレッジという植民者の名を冠した専門学校にこの養成コースがあり、私は日本からのボランティアとしてこの学校の教師をすることになったのだ。帰国子女でもなく、さほどの英語教育も受けているわけではない、業務経験3年の日本人薬剤師が、英国薬局方をその基礎とするザンビアの薬剤助手教育に、教員として平穏に従事できるはずもない。国内で薬剤師養成ができないのだから、このコースはパキスタン人薬剤師・ハニフさんとスリランカ人薬剤師・スビヤラトネさんがたった二人で運営していたコースなので、先生、足りないから、日本人ボランティアでも募集するか、ということになったのであろうか。力は足りないけれど、目の前に学生はいる。アマゾンドットコムなどまだ存在もしていない頃で、British PharmacopeiaとかBritish National Formularyとか、つまりは英国薬局方関連の書籍、薬理学、薬剤学の英語の教科書などは、面倒な手続きを経てイギリスから輸入するしかなく、ルサカのボランティアの日々は、とにかく必死で、こちらが予習して、その内容を拙い英語ながらも学生に伝え、考えてもらうことであった。
薬学部を卒業した私は薬剤師という仕事に今一つ馴染めないものを感じていて、仕事をしながら3年間夜学で経済学を学び、社会科教員の免許もとり、そのプロセスでの教育実習で教員という仕事に惹かれていた。医療関係者とはいえ、ほぼ目の前の薬のみを相手にする薬剤師より、教育関係の仕事の方が自分には向いているか、とおぼろげながら思い始めた頃だった。そんな私に「薬剤師でかつ教員」というこのザンビアでのボランティア職はうってつけのポストではあったのだが、いかんせん実力が足りず、苦労もしたし、学生にも気の毒だったが何人かの学生とは親しい心の交流があり、今も名前を覚えているPeggy Fulirwaという可愛らしい女子学生は、その後もずっと手紙をくれた。奨学金を得て、薬剤師になる勉強をしにスコットランドに行っている、という知らせも来ていた。今はザンビアを担う薬剤師の一人として育っているに違いない。いつも機嫌の良いSamはザンビアのどこかの病院で働いているだろうか。インド系学生Bayatは、エブリン・ホーン・カレッジの Bayat総長の息子であるということで随分と経済的にも恵まれた人だと聞いていた。薬剤助手にとどまらず、立派に次世代ザンビアに貢献しているだろうか。
「イムポチョレポチョレ・カウンダ(カウンダ大統領万歳)」とか「ティエンデ・パモジ(Tiyende Pamodzi:Let us go together:一緒に進もう)」とか、ザンビアの皆さんが集まれば歌っていた歌は今も耳に残っている。ザンビアに限らず、アフリカの皆さんは、ポリフォニーというか、多声音楽様式というか、一人が歌い始めると周りがどんどん声を重ねていって美しいハーモニーの合唱になっていくのは驚くべきことだった。コシ・シケレリ・アフリカ(アフリカに栄光あれ)というアフリカの解放歌がありアパルトヘイト撤廃後は南アフリカの国歌の冒頭の曲となったが、この曲はタンザニアやザンビアでも、国歌として異なる歌詞で歌われている。力強い肉声の歌で、素晴らしい国歌で、歌い始めるとみんな実に幸せそうに歌う。いいな、と、少し思う。
「カウンダ大統領万歳」の歌、とか書いたが、1980年代半ば、私がザンビアで働いていた頃、ザンビア建国の父とよばれるケネス・カウンダがまだ大統領を務めており、絶大な人気を誇っていた。彼の写真をザンビアのあちこちで見るのだが、ちょっとびっくりしたのは、女性のスカートのようにも使う一枚布にも、カウンダ大統領の肖像がばっちりプリントされているものも多く、女性の後ろ姿のお尻あたりにカウンダ大統領がばーん、とみえていることもほんとうによくあった。敬愛する国のリーダーの顔写真をお尻に敷くことは、いかなる意味においても日本では考えにくいのだが。
ザンビアに限らず、多くのアフリカの国の女性たちは、大きな一枚布をスカートにしたり、スカーフにしたり、羽織ったり、こどもたちを抱えたりするのにつかっている。タンザニアやケニアでは「カンガ」とよばれていて、ザンビアでは「チテンゲ」とよばれていた。タンザニア、ケニアで話されていて公用語であるスワヒリ語でこのような布のことを「キテンゲ」というらしいので、チテンゲはそこに由来する言い方なのかもしれぬ。コンゴ民主共和国(旧ザイール)ではビランバ、と呼ばれていた。この、一枚の布をスカートにしたり上着にしたり髪飾りにしたりすることにおいては、西アフリカの人たちの方が一層洗練されているように見える。東アフリカであるタンザニア、ケニア、そして南部アフリカザンビアでは、割とシンプルに腰巻きにしたり、荷物や子どもを抱えたり、上に羽織ったり、以外のことはあまり見かけなかった。
チテンゲは薄い布なので汚れても洗濯すればすぐに乾く。絵柄もカウンダ大統領のみでなく、大きく華やかなアフリカン・プリントのものも多くあり、美しい。机に広げてテーブルクロスにするにもよく、風呂敷がわりに物を包むのにもよく、なかなか重宝する。一枚布で使っても良いのだが、マーケットにあるテイラーなどに持ち込むと、チテンゲドレスとよばれるワンピースやツーピースに仕立ててもらうこともできた。腰巻き、と言うかスカートとしての使い方は、東南アジアのサロンなどと同じで、布の両端をひっぱって腰に沿わせ、ウエストに沿わせてきゅっと力を入れて体に沿わせていき、布の端をウエストに挟み込んだり、結んだりする。これはシンプルなようだが、慣れないと体に沿うように美しく着こなせないのは同じだ。
一枚布を腰に巻く、はアジアからアフリカにかけて、女性たちを最も美しく見せる装いだったように思っている。
 三砂ちづる (みさご・ちづる)
三砂ちづる (みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮育ち。津田塾大学名誉教授、作家。京都薬科大学卒業、ロンドン大学Ph.D.(疫学)。著書に『オニババ化する女たち』『ケアリング・ストーリー』『六〇代は、きものに誘われて』『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』『少女のための性の話』『少女のための海外の話』、訳書にフレイレ『被抑圧者の教育学』、共著に『家で生まれて家で死ぬ』他多数。