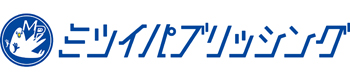- Home
- [Webマガジン]グローバルサウスの片隅で
- 「第6回 衣服にひかれていく(前編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる
最新記事
11.12024
「第6回 衣服にひかれていく(前編)」グローバルサウスの片隅で/ 三砂ちづる

あえてひらがなで「ひかれる」と書いてみた。ある衣服にひかれる。ひかれるのだ、どうしようもなく。これが着たい、これを身に付けたい、これが好きで気に入っている。それはもう一体どこからきたのかわからない。霊的なもの、としか言いようがない確かさと輝きを持って私たちに迫るので、抗えない。そのようにして私たちは、好きな服を着るのである。ある衣服にひかれる。
その時は、ただ、そう感じた、その時の直感のようなつもりでいるのだが、60代半ばまで人生も生きてくると、衣服にひかれたわけだけれども、その衣服に「引かれた」こともわかってくる。着物を着はじめたのは、45歳の時だった。ずっと着物には憧れていた。この連載の骨子にあるように私は世界中の伝統衣装が好きで、その土地に行くとそこで伝統的に着られていたものに触れるのが好きで、それが現代にも生かされているのを見るのが好きだった。日本人である私の民族衣装は着物であり、いつかその着物を日常着にしたいと願ったのは自然な流れだった。40代半ば、私の前に着物のAからZまで教えてくれる人が現れ、最初の一揃いをくださって、あれよあれよという間に私は着物を毎日着ることになったのだ。
私に着物を教えてくださった友人、ニドさんは、当時すでに着付けの師範であり、程なく日本舞踊花柳流の師範にもなられた。ピアニストでもあり、身体運動、運動科学の修練を続けている人でもあり、体のことについてもまことに造詣が深い。そういう人が私の着物メンターであったことにどれだけ感謝しても足りない。彼女の直感と、アドバイスはいつも的確な、という以上のもので、私がそれなりに失礼のない着物生活を四半世紀送れたのも、とにかく彼女のおかげなのである。
そんな彼女と最初に着物を買いにいって仕立てたものがいくつかあった。彼女のおすすめは、まず紫の一つ紋の色無地を仕立てること。これはもう、まことに正しいアドバイスであって、この紫の色無地は、慶弔両方に使うことができ、また、帯を選べば大学の教壇にも立てるような本当にマルチユーズな着物で、今もこの色無地に大活躍してもらっている。その次におすすめされたのが、「ミンサーの名古屋帯」であった。着物を毎日着たい、職場にも着ていきたい、という私に、普段着に合わせるのに最も素敵で便利で締めやすいのはこれね、と、なじみの呉服屋さんで見つけてくださったのが、黒字にオレンジや黄色を配した、ミンサー帯であった。着物を着はじめて四半世紀経とうとしており、このミンサーの帯は買い求めてから今まで、最も多く使用した帯であるが、いまだにびくともしない。
毎日着物を着て仕事に行こう、と決めたので、毎日着物を着たい。毎日のうちには晴れの日もあれば雨の日もある。どんな日にも着物を着たい、と思うと、「雨の日にも着られる着物」というのがとても重要になってくる。世間では、着物は雨の日に着ると「縮む」し、「染みがつく」ので、濡れることは厳禁、ということになっている。着物を着て雨の日に出かけるときは、「雨ゴート」を着ることになっている。雨ゴート、というのは、要するに別の着物地で作る濡れても良いコートであって、それ自体が防水、撥水、というものでは元々ないが、濡れても構わないようなものを雨ゴートにする、という感じである。私は結果として雨コートを持っていないし、使っていない。一度もらったことがあるが使わないまま、譲ってしまった。
雨コート代わりに、3000〜4000円前後といった値段で売られている着物用のポリエステルの撥水ポケッタブルコートを使っている。これはいわゆる一枚のコートになっているものもあるし、上下二部式に分かれているものもあるが、どちらにせよ、たいした値段ではない。私は雨ゴートやちりよけを着なければならない時には、このポリエステルのものを使っている。黄色の一枚になっているコートと、黒の二部式のものを持っており、それぞれ場によって使い分けている。結婚式など、色留袖とか訪問着などを着るような場でも、このポリエステルのコートを着て行って、会場に着いたら脱いで、クロークに預ければ良い。お悔やみごとなどの時には、黒い方を使う。ということでいわゆる雨ゴートは使わなかった。
さらに。普段着で着物を着る時には、ポリエステルのコート自体、着たくない。普段着の着物なら普段着の着物のまま、出かけたい。要するに濡れても良い格好で出かける方が楽だ。濡れたら拭けばいい。洋服の時と同じように着たい。そういう場合には着物では、まず「洗える着物」、つまりは、化繊の着物がすすめられてきた。私も普段着として着物を着始めた頃、これが便利ですよ、といって、化繊の着物を何枚かいただいたのだが、結局、活躍させないまま、人に譲ってしまった。化繊の着物は、確かに、汚れてもすぐ洗えるし、濡れても大丈夫だが、なんといっても、着心地が良くない。
着物を着る、というのは自然素材の気持ちよさを着るものなのだ、と理解する。木綿や絹の下着をつけて、絹の長襦袢をつけて、絹の長着を着る。あるいは木綿の長着を着る。皮膚の呼吸が助けられているような気がする。洋服は、現在は多くのものが化繊で、また、化繊の方がファッション性が高かったりするので、気づくことなくずっと化繊を身につけていたりするのだが、せっかく着物を着始めたのだから、自然素材のもので肌に馴染む感覚を大切にしたい、と、着物を着始めたらすぐ思うようになって、化繊の着物には馴染まなかった。
さらに、特に着物の初心者には、化繊の着物は着にくい。つるつるすべるのである。着物を合わせてもずれやすいし、腰紐を締めても、ずれやすい。結果として、着崩れやすいし、着付けがしにくい。これも、すぐ気がついた。肌触りというか肌馴染みが良くなくて、着崩れやすいので、いくらシルエットがきれいでも雨の日でも着られても、愛用するものとならなかった。
雨の日にも着られる着物の代表が、木綿の単衣の着物であることに気づくのに、そう時間はかからなかった。木綿と一口にいっても、綿薩摩などのように絹よりも高価で上等で、あわせに仕立てる木綿もあるが、多くの木綿は単衣に仕立てて、本来の意味での普段着として着る。今や、木綿の着物業界ではよく知られた存在になっている宮崎を本拠地とする呉服屋さん、「染織こだま」さんは、私が着物を着始めた2003年ごろ、すでに本当の意味での普段着着物、すなわち毎日働きに出られるような着物、自分で洗える単衣の木綿の着物などを手の届く値段でネットで扱っておられて随分お世話になった。こだまさんが自社開発商品として扱っておられた一乗木綿という木綿がとりわけ気に入っていた。ふんわりとした風合いで、袷の時期や真冬にも着ることができる暖かな布地である。表が黒で裏が薄い茶色になっていて、どちらの色を表にして仕立てることもできるような木綿だった。私がいつも憧れていた琉球柄、すなわちトゥイグワー(鳥)や、カキジャー(S字フックの形)などが配されていて、本当に素敵だった。つまりは琉球絣の模様で織った木綿だった。私は大柄なものも小柄なものも買い、黒を表にも仕立て、茶色い方を表にも仕立て、5枚くらいの一乗木綿の着物を使いまわしていた。袖は一寸短くして元禄袖にして、引っかかりにくくした。この着物なら雨の日も全く問題がない。やや涼しくなった頃から真冬まで、晴れの日も雨の日も、この着物なら何の心配もない。柄行も大好き。何枚もある。もう、この着物しかない、という感じ。
そして、その木綿の着物に何よりなじんだのが、先述の最初に購入した「黒のミンサー帯」であった。この名古屋帯と一乗木綿の組み合わせが、着物を着て働いた20数年、最も好きな着物の組み合わせ、落ち着く組み合わせとなったのだ。ミンサーはその名も、「綿の狭い帯」を表している、と言われる。木綿でできているから、丈夫で肌馴染みがよく、雨に濡れても大丈夫。木綿の着物に木綿の帯はどの天候にも最強なのである。
(続く)
 三砂ちづる (みさご・ちづる)
三砂ちづる (みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮育ち。津田塾大学名誉教授、作家。京都薬科大学卒業、ロンドン大学Ph.D.(疫学)。著書に『オニババ化する女たち』『ケアリング・ストーリー』『六〇代は、きものに誘われて』『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』『少女のための性の話』『少女のための海外の話』、訳書にフレイレ『被抑圧者の教育学』、共著に『家で生まれて家で死ぬ』他多数。