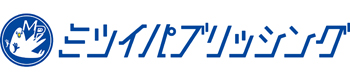- Home
- [Webマガジン]ダブリンつれづれ
- 「第13回 タゴールを探して」ダブリンつれづれ / 津川エリコ
最新記事
4.122024
「第13回 タゴールを探して」ダブリンつれづれ / 津川エリコ

セント・スティーブンス・グリーンを歩いていて偶然、インドの詩聖タゴールの銅像に出合った時、とても驚いた。銅像の存在を知らなかったのだ。この日、この公園の近くにあるホテルの前で知り合いの車に拾ってもらうことになっていた。待ち合わせの時間まで二十分ほどあった。十二月のとても寒い日だったので公園を歩いて体を温めようとしたのだった。それで思いがけなくタゴール像に出合ったとき、もう待ち合わせの時間が迫っていて足早に歩いていた。じっくり眺める暇はなかった。
それからまもなくもう一度この半身像を見ようと思いついた日があった。銅像は見つからなかった。どこか別の所へ移されたのだろうか。狐につままれたようであった。アジア食品の専門店で買い物をした手提げ袋が重かったので、早々に諦めてしまった。
とても天気の良い四月のある午後、公園の正門をくぐった。ベンチに腰掛けて新緑の美しい大木の枝ぶりをながめていると、ふと、タゴール像を探して見いだせなかった日のことが思い出された。公園の中にある筈の管理事務所に行ってこの銅像のことを訊ねてみようと思った。
ベンチから立ち上がった時、公園内の清掃をする三十歳くらいの男性に気がついた。彼は車輪のついたリヤカーのような箱型の木箱を移動させながら、公園内のあちこちに据えられている屑入れの中味をその木箱の中にあける作業をしている。それと同時に藪の中や小道に捨てられた空き缶、ペットボトルなどのゴミを一つ一つ火箸のようなもので拾い集めている。
「管理事務所はあの赤レンガの建物ですか」
私は訊ねた。
「いや、そうじゃない。あれを過ぎて道の反対側。すぐわかるよ。だけど、事務所は四時に終わるからね、今日はもうだめだ。また出直しておいで」
四月だというのに半袖を着ている彼の腕には青いトカゲの刺青が剥き出しになっている。
「そうですか、四時ですか。じゃあまた今度にしますね」
私は閉ってしまった事務所の位置を次回のために確かめておくつもりで、その方向に歩き始めていた。ふと思いついて振り返って訊いてみた。
「実は、インド人の詩人の胸像を探しているんです」
彼はにっこり微笑んだ。いいサインだ。彼は仕事柄、公園内を隅々まで知っているに違いない。
「ここをまっすぐ道なりに行ってごらん。あの赤レンガも過ぎてだよ。右側に注意を向けて」
「ありがとう。本当にありがとう」
「たぶんここから三分だ。いや二分だ」
「その詩人はタゴールと言うんですが」
彼は微笑んで頷いた。
私は歩きながら即座に自分が失礼だったのではないだろうかと思い始めた。タゴールの名を出したことである。彼が、詩人ということでイェイツの銅像と間違えてはいないだろうかと内心で一瞬疑ったのだ。イギリスを代表する彫刻家、ヘンリー・ムーアによるアイルランドの詩人イェイツの彫像がこの公園にあり、それを見るためにこの公園へ来る観光者は少なくないはずだった。ガイドブックには必ずと言っていいほど、このイェイツ像が写真で紹介されている。私が最初にインド人の詩人と言った時、彼は私の探しているものを即座に理解し自信たっぷりに微笑んだのだ。それなのに、「本当に間違いなくタゴールですか」とでも言わんばかりに「その詩人はタゴールと言うんです」などと口走ったのは余計なことではなかったろうか。ありがとう、と言えばそれで良かったはずだった。それでも彼が私の瞬間的な疑いに対して気づいた様子が全くなかったのはなんと言う幸いだったろう。
イェイツといえば、タゴールがオリジナルのベンガル語から自分で英訳した詩集『ギータンジャリ』(ベンガル語でギータンは歌、アタンジャリは合掌)の草稿は早くからイェイツの目に触れていて、これらの詩をもっとも早くから高く評価したのがイェイツだった。一九一二年、ロンドンにあるインド協会によって英語版が刊行され、イェイツは序文を寄せている。タゴールは、翌一九一三年、この一冊の詩集によってノーベル文学賞を与えられている。また、彼はナイト(英国貴族の称号の一つ。一代限り)の称号も一九一四年に授与された。ナイトの授与から五年後、インドのパンジャブで、インド市民がイギリス軍によって無差別射撃で虐殺される事件が起こった時、タゴールは称号を返上している。当時、インドもアイルランドも大英帝国の支配下にあった。帝国主義がピークにあり、アイルランド、インドの両方で独立の動きがあった。
イェイツが彼のミューズとして知られるモード・ゴンに三度求婚し三度拒絶されたことは彼自身の告白によってよく知られている。イェイツはその後、モード・ゴンの娘、イゾルトにも結婚を申し込んで断られている。イゾルトはイェイツの影響でタゴールを読み、タゴールの母語であるベンガル語を独学で学び生涯学び続けたそうだ。
一方、イェイツはタゴールの詩がいつも宗教的な祈りのような印象を与え、そこから抜け出ることがないのを不満に感じて離れて行ったようである。
清掃の人に言われた方向に向かって歩き始めてから、私は何度も来ているこの公園のこの部分をこの方向から歩いたことがない、ということに気づいた。この公園の正門はローマのタイタス門を真似て建造されている。花崗岩の巨大なアーチをくぐると左手にトネリコの老木が続く。私は、その径に惹かれてか、いつだって左手に進んで行く癖がついている。公園にはいくつか入口があり、私が使う入口は決まってメインゲートかあるいは北側の小さな鉄格子の一部が開くようになっている箇所かのどちらかである。前回、タゴールを探して見つからなかったときは、初めて銅像を見た日と同様に、意識的に北側の小ゲートから入り、長方形の公園の長い一辺に沿って鉄柵沿いに歩いてみたのだった。
清掃の人が教えてくれた通りに三分ほど歩くと銅像はあった。タゴールはギリシャのソクラテスのようにも見えた。それは私が初めに、この辺りだと思い込んでいた場所からはかなり離れていた。前回、銅像を探せなかった理由は明らかだった。私は、〈この辺りだ〉と言うことにかなり強くこだわっていたのだ。それで、銅像は他所へ移されたかも知れないなどと、突飛なことも考えたのだった。自分を信じすぎると視野を狭めてしまう。
銅像の裏へ回ってみた。二〇〇一年十月十七日、詩人の生誕百五十年を記念して、インド大使館が建立、とある。
銅像へ向かって行く間、そしてそれを再び見出した後も、公園の木々や小道や芝生、この何度も足を運んでいる公園の目に入ってくるすべてのものがとても新鮮に見えた。私はダブリンではないどこか知らないまちの公園を歩いていた。新葉を薄い緑に透き通らせる春の日差しの美しさのせいだろうか。繊細な梢の揺れの優しさのせいだろうか。私は待ち望んだ遅い春を受け入れ、そして私自身もこの地上の片隅に受け入れられているような気分だった。私には名前がない。再びどこかへ飛んでいく芝生の上の鳥であり、ほんのしばらくそこで休んでいるだけのことだった。どんな空想も許される気分だった。その気分の軽さの不意打ちこそが、その日、私がタゴールを探して得られたものなのだった。
あなたは私を終わりのないものにする
(R・タゴール『ギータンジャリ』冒頭の歌から 津川エリコ訳)
それがあなたの喜び
この脆い器をあなたは何度も空にする
常に新しい命でまたそれを溢れさせるために
この小さい葦の笛を
あなたは丘や谷を越えて持ち歩き
とこしえに新しい旋律をそれに吹きこむ
Thou hast made me endless,
(Gitanjali [song Offerings], RABIBDRANATH TAGORE, International Pocket Library, 1962)
such is thy pleasure.
This frail vessel thou emptiest again and again,
and fillest it ever with fresh life.
This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, and hast breathed through it melodies eternally new.
津川エリコ
北海道釧路市生まれ。ダブリン在住。『雨の合間』(デザインエッグ)で第55回小熊秀雄賞受賞。小説「オニ」(『北の文学2022』所収、北海道新聞社)で北海道新聞文学賞受賞。著書に詩集『アイルランドの風の花嫁』(金星堂)、随筆集『病む木』(デザインエッグ)があるほか、詩集アンソロジー”Landing Places”, “Writing Home”, “Local Wonders”(いずれもDedalus Press)に作品所収。