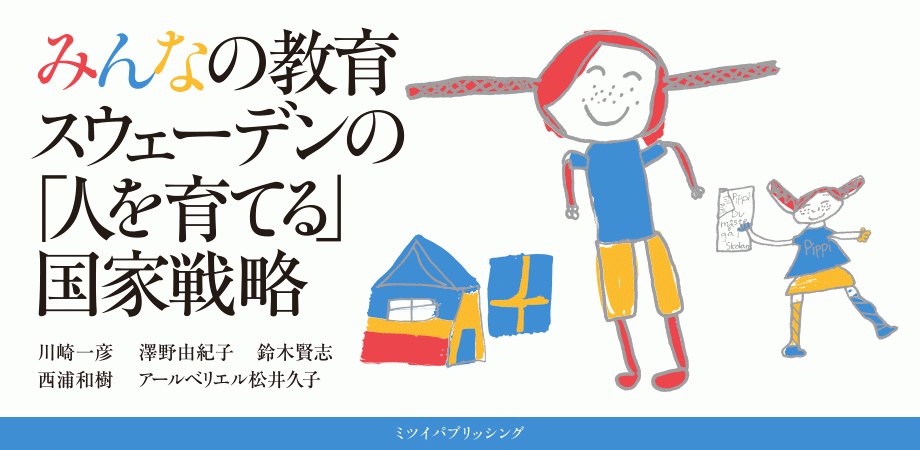最新記事
2.272018
【書評】『父の約束 本当のフクシマの話をしよう』評者:内田樹(思想家・武道家)
原発事故で生まれた日本人の“心の傷”とは?
内田樹(思想家・武道家)
極端な日本人
事故から2年半が経った。福島の原発事故について、おおかたの日本人はすでに関心を失い始めている。政治家はできるだけこの話題に触れないように努めているし、メディアの扱いも日々縮小している。日本人は福島のことを忘れたがっている。放射性物質そのものが今ももたらしつつある災禍以上に、この「関心の喪失」が日本人を蝕んでいるように私には見える。
事故の二週間後に私はこんな文章を書いた。
「貧しい環境」において、日本人は知性的で、合理的になる。「豊かな環境」において、感情的で、幼児的になる。
幕末から明治初年にかけて、日本は欧米列強による植民地化の瀬戸際まで追い詰められていた。そのとき日本人は例外的に賢明にふるまった。東アジアで唯一植民地化を回避し、近代化を成し遂げたという事実がそれを証している。
敗戦から東京オリンピックまでの日本人もかなり賢明にふるまった。マッカーサーから「四等国」という烙印を押され、二度と国際社会で敬意をもって遇されることはないだろうと呪われた日本人は、科学主義と民主主義という新しい国家理念を採用することで、わずかな期間に焦土を世界の経済大国にまで復興させた。
近代150年を振り返ると、「植民地化の瀬戸際」と「敗戦の焦土」という亡国的な危機において、日本人は例外的に、ほとんど奇蹟的と言ってよいほどに適切にふるまったことがわかる。そして、二度とも、「喉元過ぎれば」で、懐具合がよくなると、みごとなほどあっという間にその賢さを失った。
「中庸」ということがどうも柄に合わない国民性のようである。
今度の震災と原発事故は、私たちが忘れていたこの列島の「本質的な危うさ」を露呈した。だから、私はこれは近代史で三度目の、「日本人が賢くふるまうようになる機会」ではないかと思っている。(2011年3月24日)
それまでのあらゆる対立や利害を忘れて、挙国一致体制で震災被災地と福島を支援する。ほんとうに危機感があれば、それがもっとも賢明で合理的なソリューションだったはずである。
挙国一致で利益を追求
でも、日本人はそのようにふるまわなかった。菅首相は事故直後に谷垣自民党総裁に電話で「挙国一致内閣」の組閣を打診したが、簡単に拒絶された。ほんとうに国難に直面しているという危機感があれば菅首相は三顧の礼を尽くしても入閣要請をしたはずだし、谷垣総裁もその侠気に応えて受諾したはずである。どちらもつまらぬ意地や体面を優先したせいで、話は立ち消えた。それと同時に「挙国一致で復興支援と事故処理を」というシンプルな政策は事実上政治過程から消えた。
そのあと、政治家たちもビジネスマンも官僚たちも「このアクシデントからどうやってより少ない傷で抜け出すか」と「このアクシデントからどうやって引き出せる限りの利益を引き出すか」を競うことになった。政治目標が「公共の福祉」から「自己利益」に切り替わったのである。総理大臣と野党党首がその範を示したのである。日本人のほぼ全員がそれに続いたことに不思議はない。
それは重大な帰結を導いた。
以来、「福島について語る人たち」の顔を私たちは素直に見ることができなくなったのである。
どれほど切々と被害の実情について語ろうと、行政の不手際を指摘しようと、特定の個人や団体を批判しようと、「彼らはそう語ることによって、どういう自己利益を実現しようとしているのか?」という問いが、私たちの意識にまずのぼってくるようになったのである。
「猜疑心」という心の傷
「福島について語る人たち」(その中には被災者ではなく、善意で福島にコミットした人たちも多く含まれる)がどのような数値を挙げて、どのような被害評価を行おうとも、誰かのコメントを引用しようとも、それらを価値中立的なものとして受け止めることができなくなったのである。私たちは、何を聞いても、何を読んでも、そこには何らかの政治的意図が働いているのではないかと疑い深げなまなざしを向けるようになった。福島についての言説に触れるときにはナイーブであるべきではない。私たちはそのことを学習したのである。
ナイーブであれば誰かに利用される。
たしかに義捐金は行き渡らず、復興予算は被災地以外に流用された。そういう事実が報道される度に、私たちは「ただ『被災地の方たちは気の毒だ』と言っているだけでは、誰かにいいように利用されるだけだ」と思うようになった。そういう「あらゆる情報への懐疑的な構え」が、あたかも一種の「メディア・リテラシー」であるかのごとく、深く日本人のうちにしみ込んだのである。
原発事故が日本人に与えた最大の心の傷はこの猜疑心だったと私は思う。
私たちの傍らには事故の被害者たちがいる。親族を失い、家郷を失い、仕事を失い、心身に深い傷を負った人たちがいる。その人たちに対する「気の毒だ」という無防備な同情があらゆる計算に優先するはずなのである。
でも、メディアを通じて涵養された猜疑心がそのような無防備な感情の存立を妨げている。
かつて孟子は「惻隠の情」についてこう書いた。
「人にわかに孺子(じゅし)のまさに井に入らんとするを見れば、皆怵惕(じゅってき)惻隠の情あり。交わりを孺子の父母に内(い)れんとする所以(ゆえん)にも非ず、誉(ほま)れを郷党朋友に要(もと)むる所以にも非ず、その声を悪(にく)みて然るにも非ざるなり。」(子どもが井戸に落ちかけているのを見たら、人は誰でも驚きあわて、いたたまれない感情になる。子どもの父母と懇意になろうという底意があるわけではないし、地域や仲間内で名誉を得たいと思うからでもない、これを見過ごしたら非情なやつだと悪評が立つことを恐れるからでもない。「公孫丑章句上」)
何の計算も欲得ずくでもない、無防備で、ナイーブな、ただの、まっすぐな「いたたまれない気持ち」が被災者支援の感性的な基礎であるべきだったと私は思う。
でも、今の日本には、その無防備な気持ちの居場所がない。
それがこの二年半の福島をめぐる無数の言説がもたらした結果だったと私は思う。「誉れを郷党朋友に要むる」輩や「声を悪みて然る」輩があまりに多く福島について語ってきたために、「惻隠の情」のための場所がなくなってしまったのである。
「私のことはいいから」と言える人
私の手元にあるこの「父の約束」と題された小冊子では、まさにそのいどころのなくなった「惻隠の情」が奇跡的に、細々と、まだ生きている。
書き手は被災者として政府や自治体の怠業や非情を嘆くけれども、語調あらく批判するわけではない。彼にはそれより緊急な仕事があるからである。彼自身の家族を守ること、地域社会の子どもたちを守ること、彼が職業としている「障がい者」支援を継続すること、その方がとりあえず彼にとっては優先的な仕事だ。政府や自治体はいくら訴えても何もしてくれないかも知れないけれど、自分の助力を必要としている人たちのために自分にはこの場で、今すぐにできることがある。だったら、そちらを優先させる。
この小冊子が無数の「福島論」と違う、ある種の「風通しの良さ」を感じさせるのは、「自分は何をして欲しいのか」より、「自分は何をするか」が先に意識にのぼっているからである。「被害者」としての自分たちへの支援を訴えてるより先に、私のことはいいから私よりもっと弱く、もっと傷ついているものたちを先に救って欲しいと訴えているからである。彼自身が「惻隠の情」忍びがたく、「井戸に飛び込んで」いるからである。「惻隠の情」とはこういうものだということの彼自身がロールモデルになっているからである。
「弱者支援」という言葉は単純だけれど、実行することは難しい。それは「私よりずっと弱いものがいる。彼らに対して私には支援の義務があると思う」と名乗る人間によってしか担われないからである。「私は贈与するものがあるほど豊かである」という名乗りに客観的な基準はない。10億ドルの個人資産があっても「人にわけるほどの余裕はない」とうそぶく人もいるし、自分が持っている最後のパンの半分を飢えた隣人にわける人もいる。
この小冊子の書き手である中手聖一さんはたぶん「自分が持っている最後のパンの半分」を隣人にわけることのできる人である。
こういう人がひとりずつ増えてゆくことでしか福島の復興は果し得ないだろう。そして、こういう人がひとりずつ増えてゆくことを私は信じている。
孟子は「惻隠の情」が統治の基本原理であるべきだと同じ章句のうちに書いている。
「人に忍びざるの心を以て、人に忍びざるの政を行はば、天下を治むること、これ掌上に運(めぐら)すべし。」(他人の悲しみに同情する気持ちで、他人の悲しみに同情する政治を実行することができれば、天下を治めることは手のひらで転がすように容易であろう)。
何をナイーブなとせせら笑う人がいるだろう。政治はそんな感傷や理想論ではできない、と。だが、私は当今の政治家やエコノミストより2500年生き延びた孟子の知見の方を信じる。(2013年10月15日記)